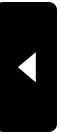2023年01月22日
剣禅話⑥

(修心要領)
「人間は、大抵は名利を求める心がひどく盛んなものである」
ほとんどの人間は欲望にまみれているものである。他人に対するにはこの事実を前提としておかねばならない。
「仁人君子の心は天地の真理に合しており、行いは人間の心の手本として強く感じ取られる。身は亡んでも心はいつまでも生き、その芳名は日月とともに光を保ち続ける」
天地の真理に逆らうことなく、正道を歩んだ人物の生き様は不滅である。
「(自分が剣法を学ぶのは)天地と同根一体であるという理を釈然と理解できる境地に到達したいという目的である」
人が求めるべき境地はまさにこの領域ではないだろうか。少なくとも自分はこの境地に強く惹かれるものがある。人間は、究極は自己の精神的完成を目指して生き、死んでゆく存在でなければならないと思う。
2023年01月20日
剣禅話⑤

(竹刀長短の是非を弁ず)
「いやしくも剣法を学ぼうとする人間は、表面だけの勝負を争ってはならない」
剣法に限らず、真理を究めようという志を持つものは、表面的な成果や評価に囚われてはならない。
(素面木刀試合の説)
「素面木刀の試合で相手を殺してしまったり、負傷させたりする人間は到底剣法の真理を修業するものではない」
肉体的な能力だけでは片手落ちであり、心の健全さに欠けるようでは粗野で暴力的なだけの人間でしかない。
(大工鉋(かんな)の秘術)
「心・体・業の三つが何事も欠けてはだめなのである」
心・体・業=心・技・体と解釈できる。これら3つはワンセットであり、どれか一つ欠けても駄目である。
【修養論】
(武士道)
「無言でもいいから実践において人倫に外れないように務めるのが武士道である」
アピールして目立つ必要はない。人倫に外れない、まっとうな実践の在り方が武士道の真実なのである。
2023年01月19日
剣禅話④

(一刀流兵法箇条目録)
「敵の方にだけ目を付けて自分を忘れてはならない。己を知り、彼をも知る必要がある」
仕合う、というの相手と自分とがついになって初めて可能であるから、自分の力量を忘れて相手に勝とうとしても覚束ない。敵を知り、己を知れば百戦危うからず、なのである。
「切り落とす、というのはいつの間にやら敵に接触する、その一瞬の拍子のことを言う」
不意に敵と遭遇したその一瞬に、無意識に技が繰り出される様、ではないだろうか?
「近いところに勝ちがあるのを知りながら遠い面を打ってはならぬ」
目前に成功可能な物事があるのに、わざわざそれを無視して博奕をすることはない。身近な成功事例を積み上げるべきなのだ、と解釈した。
「色付けとは、敵が変わった動作をするのに釣り込まれるなということである。自分が習得した横堅上下の規矩を外さないことが大切である」
相手のイレギュラーな動きに惑わされても意味がない。結局、人間は繰り返し実践して身につけたことしか実力にはならないものである。
「目で見ると迷いが生じるが、心で見れば表と裏とに迷うことはない」
視覚に頼りすぎると、対象の真の姿は理解できないものだ。言動やその周りの人間をも深く観察し、真の姿を見抜けるようになれ。
「無他心通とは敵を打とうとするのだけの心になりきれ、という意味である。他の事に心を動かさず自分が習得した業だけによって敵に当たれ」
目的のみを見定めて、自分の能力のみをその目的に向かわせれば、目的は必ず達せられるだろう。もし、達せられなくとも、少なくとも何かを得るだろう。
「残心とは心を残さずに打てということである」
もっとこうすればよかった、あのやり方のほうがよかった、等、後悔を残さないように実行するときは出し尽くせ。
2023年01月18日
剣禅話③

(剣術の流名を無刀流と称する訳書)
「一心とは内外ともに本来何物にも執着しないことを言う」
一心不乱→無我の境地、に近いのかもしれない。
「心はもともと跡形もないものであり、しかもその作用は無尽蔵である」
精神というものは物理的な形や質量をもつものではないが、それゆえに尽きることなく、無限に作用する。
(無刀流剣術大意)
「無刀流剣術は勝負を争わず、心を澄まし肝を練り自然の勝利を得ることを目標とする」
勝敗への執着から解放され、明鏡止水の如く精神状態に到達できれば、自然に相手を凌駕するのであろう。
「事理という二つのことを修業してゆく。事とは技、理は心である。事と理が一致するところ、これを妙処と考えよ」
技術と心、行動と理念、言論と実行、これらは全て一致することではじめて真実となる。
「無刀とは心の外に刀はないとすること。刀ではなく心によって相手の心を打つことを無刀という」
剣で相手の身体を打ったところで真の勝利たりえない。相手の心を上回ることが真の勝利なのである。
2023年01月16日
剣禅話②

(剣法正邪弁)
「敵の好むようにしていって勝ちを得るところに極意(剣法の正伝)がある」
相手の得意分野に敢えて挑んで得るのが真の勝利という意味だろうか。
「(諸流の剣法を学んでいる者は)血気にまかせて進んで勝つことを考えるのだが、このような剣法を邪法という。(このような剣法修業では)結局、無益の(労)力を費やすこととなる」
「そうなるのは邪法ということを反省してみないからで、道を学ぶ者はこの点を深く考えて修業鍛錬しなければならない。これらのことは単に剣法の極意だけに限らない」
どんな事柄でも、正しい方法、まっとうなやり方を常に意識していないと誤った労力・努力をしてしまいがちだということであろう。
(無刀流と称する説)
「剣法をギリギリと追い上げていったところの到達点は無敵の状態になることである。優劣の考えが自分の中にある時は無敵の状態とは言えない」
いまだ自分の心の中に他人と比較し優劣を思う気持ちが残っている時は増長してはいけない。上には上がいるのだから。
「修業者が数十年の苦行を続けても、尚、身体の働きと太刀の運びのことにばかり気を取られているのはよくない」
数十年も努力し続けたなら当然精神性の向上に向かうのだが、その時点でもまだ『技術』に心を奪われているようなら、その努力は邪法である。
「心を留(とど)めれば敵はあり、心を留めなければ敵はない」
敵認定しなければ、自然に周りに敵はいなくなるのだ。