2021年07月30日
十八史略(5)
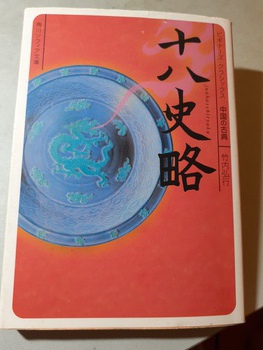
【第四章 統一の時代】
秦・始皇帝の中華統一からその崩御、秦の滅亡までを記している。
始皇帝の天下統一へ重要な役割を担った人物の一人に呂不韋がいる。彼が宰相になると、当時最高レベルの学者を秦に集めて「呂氏春秋」を編纂した。これは学術上の天下統一を成したと評されている。
「泰山は土壌を譲らず、故に大なり。河海は細流を択ばず、故に深し。」(秦の重臣、李斯の言葉)
(泰山は土くれすら他に譲り渡さないので巨大な威容を誇る。黄河は小さな流れも選り好みせずに受け入れるので深い。)
李斯が秦王に、有能ならば出身国にとらわれずに、広く人材を登用するように進言したときの例えである。
(「焚書坑儒」の際に始皇帝の長男・扶蘇が言った言葉)「言論を弾圧すると、社会が不安定になりますぞ!」
これは現在も当てはまるのではないか。北朝鮮やミャンマーのような独裁国家、軍事政権国家、更には現中国のような覇道を歩む国家、ロシアのような特殊な国をすぐに想像してしまう。秦も結局は崩壊してしまうが、先に挙げた国々も、いずれは崩壊するであろうことは想像に難くない。
始皇帝の性格は生まれつき強情で何事も自分でやらなければ気が済まない性格であったらしい。この点、叩き上げの創業者に気質が似ている気がする。そして、その強権的なトップが不慮の死などで欠けると、たちどころに組織が傾く点も似ている。
組織が大きくなったら、分業・分担を進めることが組織存続のカギであるのかもしれない。
十八史略のみならず、中国歴史の真髄は「天網恢恢疎にして失わず」というめぐる因果でバランスをとっているし、そこが言わんとしていることであろう。
(十八史略 終わり)
Posted by godman at
09:46
│十八史略(ビギナーズクラシックス)
2021年07月29日
十八史略(4)
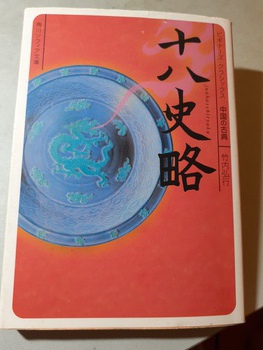
管仲や晏嬰は、行使にとって理想の政治家像そのものであった。管仲、晏嬰に子産を加えた三名が、春秋時代の三大名宰相といわれている。
「良賈は深く蔵して虚しきが若くし、君子は盛徳有りて容貌愚なるが若し」(孔子が礼について尋ねた時、老子が答えた言葉)
(一流の商人は収益(成果)を奥深くしまい込んでまるで儲けていないようにしている。優れた人物は、素晴らしい徳(能力)を身に付けていてもそれを表に出さないので、外見はまるで愚かな人物のように見える。これが礼の極意である。)
アピールや作為を否定し、敢えて自然体のままでいて不要の批判を受けないことこそ、礼の極意ということらしい。凡人はついつい成果を誇ってしまうものだが、この戒めは肝に銘じておくべきだろう。
「子の驕気と多欲とを去れ。態色と淫志とはこれ皆子の身に益なし。吾れ子に告ぐる所以はかくのごときのみ。」(老子が孔子にした忠告)
(孔子よ、君の満々のやる気と種々の欲望を捨て去りなさい。意欲にあふれた態度も意志も、君の身体によくない。私からの忠告はこれだけだ。)
孔子は、積極果敢な行動家の面があったようだ。老子はそれを見て周囲との調和に不安を感じたのではなかろうか?自説を頑強に信じ、理想を追い求めすぎるきらいがあったから、恐らく仕えた主君との軋轢を心配し、焦るなと言いたかったのだろう。(実際、孔子は仕官先で主君や重臣に疎まれ、長い放浪生活を強いられる)
能力のあるものは自らの力に自信があるがゆえに、この落とし穴にはまりやすい。
配下の者が、二重基準を設けて民へ「大衆迎合」することは下剋上、主従転覆の原因となるので、させてはならない。(田氏台頭の原因に鑑みて)
様々な人物がイキイキと自由に活躍できたのが、戦国時代のもう一つの側面である。
Posted by godman at
14:11
│十八史略(ビギナーズクラシックス)
2021年07月28日
十八史略(3)
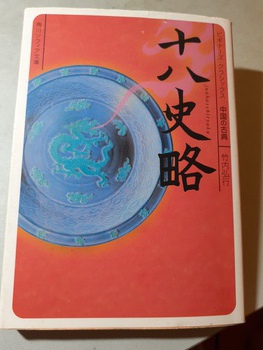
【第三章 争覇の時代】
秦による統一までの、中国の春秋戦国時代についてまとめられている。この時代こそ、中国史で最も面白い時代である。
(宋の景公の言葉)「宰相は自分の手足と同様に大切である」「君主は民に支えられているものである」
(景公の言葉を聞いた子葦)「天は空高くにおわしますが、低き地上のことをよく聴きつけるといいます。景公の心掛け、天がしかと聴きつけて願いをかなえてくれましょう」
(斉の名宰相、管仲の言葉)「私を生んだのは父母だが、私のことを知り尽くしているのは鮑叔牙である」(無二の親友の典型)
(管仲ののち、斉の宰相となった晏子(晏嬰)を評して)「晏子殿は、身分は斉の宰相であり名声は諸国に知れ渡っておられるが、その本志はいつも人に遜って謙虚であられる」
Posted by godman at
13:46
│十八史略(ビギナーズクラシックス)
2021年07月27日
十八史略(2)
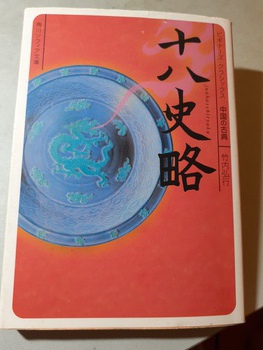
(禹の言葉)私は天命を受けて王となり、努力して万民を慰労してきた。この生は寄(かりそめ)のものであり、死こそ帰りゆく処だから、何の畏れもない。(夏王朝の祖、禹が長江を渡ろうとした際に竜が現れ、船を転覆させようとし、まさに絶体絶命の場面でありながら、泰然と言い放った言葉)
【第二章 聖君から暴君へ】
夏桀殷紂の故事について記述されている。酒池肉林、炮烙の刑など、様々な悪逆を行ったがゆえに革命によって王朝が倒されたことが書かれている。
Posted by godman at
10:48
│十八史略(ビギナーズクラシックス)
2021年07月26日
十八史略(1)
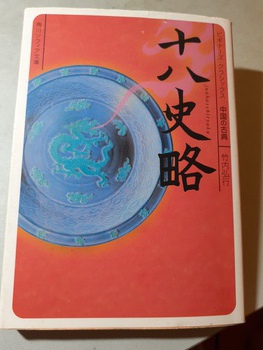
(解説)
十八史略とは、十八種の歴史書の概略という意味である。元朝時代に編纂されていて「前事、忘れざるは後事の師なり」、つまり過去の事実を忘れずに、それを踏まえて考えれば将来予測の指針となる、という考えで書かれている。
【第一章 聖人の時代】
黄帝、堯、舜、禹、の伝説の時代を指す。黄帝の世では「無為の治」すなわち「何もしないでいて万事が思い通りの世の中になること」が実現されていたとされる。これは、中国における最高の政治形態と長くされてきており、国主が存在せず、国民が無欲で、自然のままの暮らしで豊かさに満たされた世が理想像であった。
(堯の言葉)男子が多いと心配事も多くなり、富貴になると揉め事が多くなり、長寿だと屈辱を受ける機会も多くなる。(天から天子に指名された際、固辞する理由として述べたもの)
Posted by godman at
10:14
│十八史略(ビギナーズクラシックス)










