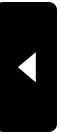2024年11月24日
宋名臣言行録⑫

(第二章)
會公亮 は、詔勅条例に全部目を通し、帳簿類を突き合わせ、善悪可否を区別していい加減に放っておくことはなかった。
「学問は世事を正す目的のものである。」(王安石)
「書物は暗誦しなければならぬ。馬の上に居ても、寝付かれぬ夜半も、いつも文章をそらんじ、その意味を考えていれば得るところが多い。」(司馬光)
「考え深い人間は、浮世離れして見えるものだ。」
2024年11月23日
宋名臣言行録⑪

「法を変えることは昔から難事である。祖宗の成法を守る努力もせず、ただ思い付きでやっても治世の利益にはならない。」(胡宿)
「外敵と上手に外交するには、日頃から備えを怠らぬことにかかっている。」(胡宿)
「富貴貧賤は全て天命である。士人たる者は自分の身を修めて時節を待ち、天から嗤われないようにすべきである。」(胡宿)
*胡宿は日頃から正道を遵守し、出処進退に心を煩わされなかった。
*人は、自分の出来ぬことを他人がやれば、頭を下げざるを得ない。
2024年11月22日
宋名臣言行録⑩

「人の才能や性質は様々である。長所を利用すれば物事はやってゆけるものだ。無理に短所を持ち出すと先ず上手くゆかぬのは必定である。」(欧陽脩)
「民を治めるのは病気を治すようなものだ。事務能力の有無、計画や施行の如何を問わず、民が『これは善い』と言えばそれがつまりは良吏である。」(欧陽脩)
「私が言う大まか、とは過酷とか急がせることをしない意味であり、簡単、とは煩雑瑣細な事を避けるにすぎない。」(欧陽脩)
2024年11月21日
宋名臣言行録⑨

(第二部 三朝名臣言行録)
(第一章)
韓琦 は一人でうだつの上がらぬ財庫管理に留まり、人々の同情をよそに平然としてその職を務めて卑下せず、職事をつゆほどにも疎かにしなかった。
「選択が難しい場に立たされた時は、強引に事を進めて後にしこりを残してはいけない。」(韓琦)
「上に引き上げるのはたやすいが、降格させるのは難しい。」(韓琦)
「才知器量の有る者はオールマイティであるべきだ。大きい粗いことも、小さい細かいことも出来て初めて天下の事業が取り仕切れる。」(韓公)
2024年11月20日
宋名臣言行録⑧

王堯臣 は、国家財政の出入伸縮を分析し、「これは根本、あれは枝葉」と重要性や緩急の度合いを測り、根本的弊害を除き、無意味な施策や、小さな利益はあるが大きな本質を損なうもの、をしりぞけてから実施の条目を使って法規と組み合わせた。
「外の評判というものは安直なものだ。辺境でやるべき施策をし尽している責任者を意味もなく代わらせると、必ずや自己の聡明さを見せびらかす為、あれこれ変わったことをやり、前任者の実績をぶち壊してしまうものだ。」(王旦)
王質 は宰相の一族だったが、威張らず飾らず、貧乏を大切にしていた人物であった。
「気に入った場所にいつまでも引きずられるな。上手くいったところには二度と足を向けるな。」(陳摶:ちんたん)