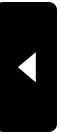2021年04月01日
資治通鑑(4)

【清流と濁流~巻55・56 漢紀より~】
智者ぶりは他人に真似が出来ても、愚者ぶりは真似出来ないものである。
(格好つけて体裁をごまかすことは出来ても、自らを愚かしく見せることは常人ではできないものである)
(世の乱れが極まっている情勢の中で、孤軍奮闘する事の無謀を嘆いて)例えば大木が倒れかけているとき、一本の縄ぐらいで繋ぎ留められるものではない。なぜバタバタと慌てふためなければならないのか?
臣下たるもの、計謀あれば決して隠さず、罪あれば刑(しおき)を回避せぬもの
(人に使われている立場の者は、アイデアや方策を思いついたなら隠さず進言し、また、ミスや損害を生じさせたら速やかに申告することがあるべき姿である)
「君に仕えては危難を回避せぬ。罪があれば刑(しおき)免れぬ。それが臣下の操というもの。ワシはもう六十じゃ、人の生死には定めがある。逃げろったってどこへ行くのだ。」(八俊の一人、李膺の言葉)
目出たき評判を博した上、更に長命を望むなど無理というものだ。
(人間、細く長くか太く短くかのどちらかなもの。あれもこれもと望んでも叶うわけがない)
2021年03月31日
資治通鑑(3)

(一般に、人というものは)人格者へは畏敬ないし警戒の念を覚え、才走った者へは愛情を寄せるものだ。
(人格者は偉い人であり、どちらかというと遠い存在であるのに対し、才走った者、すなわち才子はその優れた点が見えやすいため親近感を抱きやすいということ)
(主君が)才能と人格の区別をつけ、いずれを優先するべきかを心得ていればその人物を見損なう(見誤る)心配はないものだ。
(組織の長が人事を行う際、その才能と人格を的確に把握していれば、適材適所を実現できる。その判断が出来るトップであれという戒め)
2021年03月25日
資治通鑑(2)

頭が切れて精神面で逞しいのが「才」、真っ直ぐで調和を保つのが「徳」。才とは徳の資材であり、徳とは才の指揮者である。
(何よりも徳が第一)
才、徳ともに完全無欠であるのが聖人であるが、ともに欠くのは愚人である。また、徳が才に優越するのが君子であり、逆が小人である。
(才走り過ぎているものを資治通鑑の著者、司馬光は認めていないのではないだろうか)
小人をつかむ(従える)よりは愚人をつかむほうがマシである。なぜなら、愚人の悪事は(被害を被る前に)難なく取り押さえることが出来るが、小人のそれは、悪知恵で固められ匹夫の勇もあり、甚大な被害を及ぼすからだ。
2021年03月23日
資治通鑑(1)

本日より、資治通鑑を読み解いていきます。
といっても、原著が想像を絶するものすごい量の書籍なので、テキストの部分だけですが...
【才と徳:巻一、周紀より~人物鑑識のポイント~】
人より優れた五つの長所を持ちながら、人間愛(仁)に欠けた冷たい心で行動する者に、将来性は無く、トップとしての器量も無い。
(人の上に立つ資質は、何よりも仁の心を持っているかどうか?という一点のみ)
人が過失を三度繰り返すと、必ず怨みを買う。その怨みは顕在化した形をとるとは限らない。顕在化せぬ怨恨に対する策を講じておけ。
(直接的な報復よりも、怖いのは素振りも見せない怨み。それを想像して細心の注意を払っておくべきなのだ。他人の表に出る表情を過信するな!ということだろう)
才と徳は違った(性質の)ものであるのに、世間一般(の人々)はこの二つの区別をつけられず、(才のみしか見ないで)おしなべて「賢人」、すなわち立派な人物だと言う。これが人品を見損なう原因である。
(才能と徳性は同一ではなく、序列・順位があるもの。才能という目立つ部分ばかり見て人を評価すると、見誤ることが多いという戒め)