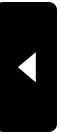2021年05月13日
晏子春秋(6)

「その人物を判断するには推挙登用する人物を見るとよい。善人なら善人を、悪人なら悪人を、小人なら小人を推挙したり、登用するものだ。」
(人物評価の方法の一つとして、当てはまることが多いのではないかと思う。)
「君子は困窮しても節操を変えないものだ。また、富んで独占せず、貧しくて廉潔を守る人は人格者である。」
(願わくは、このような人間になりたいものだ。しかし今の世の中、このような人を目の当たりにすることは絶無に等しい。)
*明王の政教大綱は、教令を明確にすること、率先して義を行うこと、民の利を守ること、である。
(政治に求められていることは、今も昔もこのシンプルな事柄に集約されていると思う)
「人の長と巧を知って、これに応じて職務を与え、人の短と拙を責めないのが人材任用の要点である」
(長所と得意分野を見極めて適所を任せること、短所や苦手は目をつぶるようにすることが、その能力を正しく発揮させることにつながると言える。)
2021年05月12日
晏子春秋(5)

「天下を服するのは勇力ではなく徳行である。民を愛する事、人の死を重んじること、裁判を公平にすること、賢者を任ずること、仁義を尊んで世の中に諮ることを実行しなくてはならない」
(国家というものは力で制圧・統治できるものではない。人民を愛し、人命を尊重し、公平な社会を作り、能力のあるものを適材適所で任用し、思いやりと正しさを重視した政治を行い、その評価を世の中に諮ってみることだ。)
「徳によって国内を安んじ、政治によって民を和合せしめて後に他国の暴逆を征すべしとなすのは古今の通則である。」
(他国へ攻め入る前に、先ずは自国をしっかりと安定させることが優先事項である。某国のように自国の乱れを他国への敵対で誤魔化す国家はいわば悪である。)
*『自国の政治を修めて、他国が乱れるのを待つ』というのは兵法の極意である。また、国政に災いを招くのは①社鼠(組織に巣食う小人)②猛狗(地位に固執する実権者)の二者である。
2021年05月11日
晏子春秋(4)

「言うところの賢あって知らず、知って用いず、用いて任せず、というのは人材登用における三不祥である」
賢者の存在を認識していない事、認識していても招致しない事、承知しても信任しない事、この三つは人材登用におけるタブーである。
「人の死を送り葬を営むことは万人の心情の自然である。これを侵すことは人間性にもとる」
(自然な万人の感情は無視できないことを述べている)
*礼の尊重は暴力の否定である。それは個人においても社会一般の場合でも同じである。礼(というもの)は具体的行為を通じて示される。
(儀礼というものには本来しっかりとした意味があるということだろう。やみくもに否定するのは良くないかも知れない。)
2021年05月10日
晏子春秋(3)

「明王は徒(いたずら)に立たず、百姓は虚しく至らず」
明君は無意識に(自覚なしに)その地位に甘んじてはいけない。人民の心を以って我が心としなくてはならない。
また、人民は理由なく君主に従属したりはしない。有徳の君主でないと心を寄せるものではない。
(いつの時代も、為政者や組織の長は、自分の立場をよくわきまえて責任や責務を謙虚に自覚していなけらばならないものである。
傲慢で思いやりのない無責任なトップの下では、どんな人材も必ず離反してゆくし、誰からも協力を得られないのは普遍的事実である。晏子は常に民の心になって意見を述べている。)
*絶対君主にとって、意のままにならないのは「死」だけだが、彼が永久に死なず国を保有していたいという欲望は、後の明君たるべきものに対する不仁である。(これは組織のトップにも当てはまるだろう。『老兵は死なず、ただ去るのみ』なのだ。時期が来たら勇退しないと、後進が育たず、組織の発展もない。)
*景公は、人民に重税を課し、命令に従わないものを厳罰に処する政策をとったので、徴税事務と訴訟手続きがやたらに煩雑になってしまう。それを晏子はやんわりと諫める。優れた政治家は優れた人心の洞察者である。
(なんでもかんでも規制し、制限し、厳罰化しても、そこに民衆の同意が得られなければ国勢は衰えるばかりである。優れた政治家は人心がよく見えるものだ。)
2021年05月08日
晏子春秋(2)

「それ賤をもって貴に匹するは国の害なり。大を置いて小を立つるは乱のもとなり」
嫡出子と庶子の区別と、長幼の順序とを基準にしてお家騒動の芽を未然に防ぎなさいという諫言。
現代社会には必ずしも当てはまらないと一見思える。しかしながら、的確な価値基準と重要度の把握が、物事を判断する際には大切であると読み取ると今の社会にも通用してくる。
平和で安定した時代を作るには何より判断の正しさと的確さが必要なのである。特に情報の濫立している今の世の中では、非常に重要な事柄である。
*晏子のものの考え方は常に現実的、実際的である。神明を否定はしないが、それに頼るよりもまずは努力と修練に努めよ、と一貫して述べている。このあたりも名宰相と呼ばれる所以であろう。