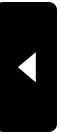2021年11月29日
菜根譚(10)

「周囲の人の元気を失わせない」
短気で気性の荒い人は周りの人を怯えさせてしまう。人情味の無い人は周りの人の気持ちを寒々とさせてしまう。頑固で融通の利かない人は周りの人の活力を奪ってしまう。
*短気で気性が荒い、人情味が無い、頑固で融通が利かない、このような傾向の者は反省し改めなくてはならない。また、このような人には近付かないことが得策である。
「信念を人に押し付けない」
人の上に立つ者はその信念を曲げてはいけないが、無理に人に押し付けるのもよくない。
「人を責めない」
人間関係において、①他人の小さな過失を咎めない②他人の隠して起きたい私事を暴かない③他人の過去の悪事をいつまでも覚えていない、ということに留意すること。
*重箱の隅を突くように他人の負の面ばかりを見てはいけないということ。他人にはある程度寛容でないといけない。
「新しい友人をつくるより古い友人を大切にする」
人生をよりよく生きるには、①他人に恩を着せず、常に公平公正な態度を貫くこと②旧知の古い友人との付き合いを大切にすること③人知れず世のため人のために尽くすこと④日常の行いは慎み深く、という心掛けが必要である。
「人の弱点を責めない」
他人の欠点や短所を見つけても、出来るだけ上手にカバーすることがその人の助けになる。
*人間だれしも欠点、短所はある。自分だけが完璧ということはあり得ない。他人の欠点や短所をカバーすることが、自分の欠点や短所をカバーしてもらうことにつながる。
2021年11月26日
菜根譚(9)

「いざ、という時の為に普段から精神を鍛える」
死に際になって取り乱さないよう、日ごろから物事の本質・道理を見極めておくことだ。
*絶体絶命、最期の状況にあって冷静に客観的に振舞うためには日々物事の本質を掘り下げて視る訓練が必要である。
「夢中になりすぎない」
心が何ものにも囚われなければ俗世間も理想郷となる。心が何かに執着してしまえば楽しみすら苦しみに変ってしまう。
*執着は貪欲を呼び寄せる麻薬のようなものだ。
「忙しいときは冷静になり、暇なときは情熱(モチベーション)を持て」
「騒がしさも静けさも超越する」
喧騒を嫌い静けさを好む者はとかく人を避けるが、そういうこと自体がそうした環境(静かな環境)に依存し囚われている証拠である。こんな現実逃避をしている様では【自他を区別することなく動も静も超越する】境地へは到達し得ない。
*好む環境に逃げ込むことが悪いのであって、好むこと自体は悪くないと思う。喧騒の中でも静けさを見つけられる人は稀であろう。
「相手の受容量を考えて指導する」
人を育てる時、目標を高く掲げれば良いというものではない。相手が実行できる範囲か否かをしっかり考慮して適正に導くことである。
*人材育成のための訓戒である。画一的な指導では人は育たない。個々に合わせたきめ細かい指導こそ真の教育なのである。
「つまらない人物を憎まず、立派な人間に媚びない」
つまらない人間に対して短所や欠点をあげつらい厳しく接するのは簡単だが、憎まないというのは難しい。
*小人は欠点が多くあるから小人である。ダメなところを見て毛嫌いし憎むのは生産的ではない。当然のことと割り切るしかない。立派な人間であっても同じ人間である。尊敬しても媚びてはならない。媚びることは人格を卑しくしてしまう。
2021年11月25日
菜根譚(8)

「全てを自分の責任と考える」
素直に反省できる人はあらゆる経験・体験を全て自分磨きの良薬に出来る。謙虚に反省しそこから学ぶことの出来る人間は成長できる。
*なんでも他人のせいにするような甘ちゃん、未熟者は成長できず、いつまでも精神的に幼いままである。
「非凡や高潔を気取らない」
わざと非凡な人間を気取るのはただの変人に過ぎない。世を捨てて高潔を気取るのは単なるひねくれ者に過ぎない。
*気取ることに問題がある。ポーズだけで中身が伴わなければ何の価値も無い。
「功績や知識を誇らない」
功績にしても学問にしても、人に見せびらかすのはまだ人として成熟していない証拠である。
*承認欲求が強いのは未熟の表れである。
「他人からの迎合に気を付ける」
誹謗中傷されても時が経てば事実は明らかになり汚名は返上できる(だから気に病むな)。しかし、『へつらい』や『迎合』には気を付けよ。気づかぬうちに自分をダメにしてしまう(だから遠ざけよ)。
*ご機嫌取りは近づけてはならないということ。必ず下心があるものだから。
「口に出す前によく考える」
口は心の門、だからこそ意識して(発言は)慎重にしなければならない。意識は心の足、だからこそ行動を起こす前に何が正しいかしっかり考えなければならない。
*発した発言は取り消すことが出来ないし、やってしまったことは元には戻らない。後悔・失敗をしないためには慎重さと熟考を要する。
2021年11月24日
菜根譚(7)

「与えた恩は忘れ、受けた恩は忘れない」
人に与えた恩は忘れよ。しかし掛けた迷惑は決して忘れるな。人に受けた恩は忘れてはならない。しかし受けた恨みは忘れよ。
*本来、「恩」は見返りを求めるものではないから与えた側はきれいさっぱり忘れることだ。受けた側は感謝の意を持ち続けていればいい。迷惑を卦けたことに対しては陳謝の気持ちを忘れてはならないが、他人からのひどい仕打ちは、仕返しする労力が勿体ないから忘れてしまえ!
「エリートとしての自覚を持つ」
真のエリートとは世の中の為に働こうという強い意志と社会的責任を自覚している者を言う。選ばれて社会的に高い位につき豊かな生活を保障されていながら人の為になるような発言も仕事もしない者には値打ちはない。
*泥を被る覚悟も無い、社会的地位が高いだけの、地位と禄を貪っている者への批判。能力のすぐれた者こそ、その能力を民衆や社会の為に発揮すべきであって蓄財に励んだり私欲を得ようなどもってのほか。今の政治家には耳が痛い言葉であろう。
「極端に走らない」
志は高くあるべきだが、現実離れしてはならない。思考は注意深くあるべきだが細部にとらわれ過ぎてはならない。感情は淡々とあるべきだが冷酷ではいけない。信念は厳しく守るべきだが頑なになるべきではない。
*何事も極端に走ると必ずや反動・副作用が生じるもの。現実乖離、本末転倒、方向性逸脱に陥らないよう常に自身で省みることだ。
「他人の才能を妬まない」
自信過剰になって勇み足になってはならない。自分の長所を吹聴し他人の短所を暴き出すようでは駄目だ。自分が無能だといって、他人の才能を妬んではならない。
*自分の長所を大きく見せそれによって他人の短所を炙りだしたり、敢えて無能だとへりくだったふりをして(自分より優れている)他人の才能を妬むだけの怠け者は全てにおいて中途半端なものである。
「怒りを表さない」
怒りを感じても顔色一つ変えず平然としているような態度にその人の度量の大きさが表れるし効果も大きい。
*怒る者は測るべきも笑う者は測らざる、ということであろう。馬鹿にされ、見下されてひどい言葉を投げつけられても、嘲笑されても、意に介さず笑い飛ばせるようなら、かえって相手は不気味さを感じ、態度を改めるものである。
2021年11月22日
菜根譚(6)

「心を落ち着ける」
心が落ち着いていれば、全てのものをありのままにとらえることが出来る。
「才能をひけらかさない」
人格者と言われるものの特徴は、一つは誰にでも公明正大で自説や価値観を明白に出来ることであり、もう一つは才能を奥深くに隠し、決して他人にひけらかしたり目立つような振る舞いをしないという点にある。
*自説や価値観を明白に出来るということは、自分の中で確固たる基準を持っているということだし、目立つような振る舞いをしないのは、へりくだる心の余裕があるということであろう。
「無事な時には心を引き締め、有事の際にはゆとりを持つ」
上手くいっている時こそ油断しない。多忙な時ほど気持ちにゆとりを持ち冷静になれ。
*迂闊にはしゃいで有頂天になったり、簡単に落ち込んで自暴自棄になったりするのは人格が練れてない小人である。
「おごり高ぶる心を捨てる」
思い上がりを捨て、謙虚に自分を見つめてこそ真の自信が生じる。心の迷いを消し去った時、初めてその人本来の心が現れる。
「富や名誉の誘惑に負けない」
人格に磨きをかけたいと思えば富や名誉に溺れない無欲な心が必要である。又、政治家を志し国の為に力を尽くしたいと思えば、何ものにもとらわれない自由な心が必要である。