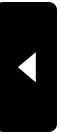2021年12月04日
菜根譚(15)

「小さなことにも手を抜かない」
①小さなことにも手を抜かない(全力)②人が見ていようがいまいが悪いことはしない(節度)③失意の底に沈んでも決して投げやりにならない(不屈)、これが立派な人物の要素である。
「周りをよく見る」
目新しく風変わりなものばかりに飛びつく者は深い見識に欠ける。意見に耳を貸さず、ひたすら我が道を行く者は最終的に志を全う出来ない。
*落ち着きのない者は信念がブレるし、頑固過ぎる者は道を誤りやすい。
「個人的な利害は忘れて物事に取り組む」
物事を実行に移す際には個人的な利害損得は一切忘れるべきである。
*目先の利害に囚われると、正道を踏み外してしまうものだ。
「時間をかけて慎重に行う」
起業の際は重く強い弓を放つ時のように慎重を期すべきである。軽々しく始めてしまうと大きな成果は得られない。
「本質に迫るまで深く学ぶ」
本を読む時はその真髄や精神を感じられるまで読み込まねばならない。物事を観察する時は対象と一体になるまでじっくり見る。それが本質に近づく道である。
2021年12月03日
菜根譚(14)

「初心に返る。行く末を見極める」
行き詰まったなら、初心に返り失敗の原因をじっくり考えよ。成功を収めたなら、行く末を良く見極め、自分の引き際を決めておけ。
*物事が行き詰まるというのは、その過程のどこかに原因があるからスタート地点まで遡ってみて検証するとよい。物事が成功し、軌道に乗ったならば、その終点を冷静に見極めどのように退くかを決めておくべきである。成功に執着してはいけない。
「本来の目的を見失わない」
事業を興しても(本来の目的を忘れ)利益ばかり追求して利己的であるならば、いずれは社会から淘汰される。
*事業というものは社会的に有益でニーズが有るならば成長できるし存続し得る。利己的で利益のみ追求するような姿勢では長続きしない。
「自己顕示をしない」
清廉だと評判が立つ人は、実はその清廉を自ら売りにしていたりする。又、自分の技術・知識を人前でひけらかしているようではまだまだ未熟の域を脱していない。
*ひけらかすという売名行為を、意図的であろうと無意識であろうとしてしまう者は、いわば自分に酔っている状態で冷静さを欠いている。そのような状態ではまだまだ人間的に未熟である。
「楽しい事は程々にしておく」
遊びや楽しみ、美食は夢中になりすぎると身を誤る。程々にしておけば後悔は少ない。
*趣味に熱中しすぎると本業が疎かになり、生活基盤を脅かす事となる。美食に溺れると健康を損ねて寿命を縮める原因となる。
「正義に逆らわない」
公平な意見や正当な論理に反対してはならない。末代までの恥となる。権勢家・私腹を肥やす者に近づいてはならない。生涯の汚点となる。
*意見や論理、その正しさを理解できない人間は世の失笑を買い、一族郎党笑いものとなる。不純な存在である権勢家や私腹を肥やす者とは、純粋な人間関係を築くことは出来ず、社会から非難される羽目になるものだ。
2021年12月02日
菜根譚(13)

「本質を理解する」
形のみにとらわれ、その精神(や本質)を理解しようとしなければ物事の真髄に迫ることは出来ない。
*しかし、現代人は形のみで満足している者が多いと感じる。
「社会生活の中で悟る」
人としての正しい道を極めるのに隠遁生活は必要ではない。普通の社会生活の中でもその方法は発見できる。
自分の本質を知るために、全ての欲望を絶つ必要はない。心を静かに見つめ直すことで分かるものである。
*日々の生活の枠の中で、心を落ち着けて自身を見つめ直す時間は非常に有益ということだろう。
「無心の境地を楽しむ」
自分が死んでしまった後、名誉や地位、財産などへの欲心は全て消え、残るのは自分本来の精神のみである。その心境に至れば現実・世俗を離れた高みに往きつく。
*手に入れた物への執着から解き放たれることが、無心の境地への入り口である。
「客観的に物事を見る」
物事の渦中にいても、心はその場から切り離し冷静な判断が出来るようにしておかなくてはならない。
*どんなに忙しい状況にあっても、状況を俯瞰し、冷静に判断し続けるのが有能の士である。
「動きすぎず、静かすぎない」
活動的過ぎても雲間に見える稲光や風に揺らぐ灯火の如く、持続性に欠ける。静寂ばかりを好んでいると灰や枯れ木のように生気が失われてしまう。
*物事に対して動きすぎても駄目だし、動かなすぎても駄目なもの。何事もバランスを考えて静動・硬軟を使いこなすことが成果を成す。
2021年12月01日
菜根譚(12)

「リーダーになったら言動に注意する」
①発言は公明正大に、態度は公平公正を貫くこと②常に心を穏やかに、笑顔で部下に接すること③権力を欲する者や利権屋には近付かないこと④極端に走り、恨みを買うようなことはしないこと、これがリーダーの心得である。
*リーダーになったからと言って急に変えるのではなく、常日頃から実践していなければすぐにボロが出るものである。リーダーであろうとなかろうと心にとめるべき心得である。
「公平さを保つ」
公平さは判断を明快に正しくさせる。清廉潔白であれば態度に威厳が備わる。日頃慎ましく暮らしていれば生活にゆとりが生まれる。
*狡猾さや贅沢を排除すれば、人生は穏やかで充実したものとなる。
「利己的にならず大局的に判断する」
多くの人から反対されても、自分の意見を簡単に変えてはならない。自説を正しいとして他人の意見を排除してはならない。えこひいきで全体の利益や大局を損なってはならない。個人的恨みを晴らすために世論を利用してはならない。
*ある程度の頑固さは必要だが聞く耳を持たないのは欠点となるし、我に固執しては損害や悪名を受けるはめになる。
「世の中は思いのままにならないと知る」
思いがけないことが起きたり、全く想定外なことだらけなのが世の中である。人間の浅知恵や企みなど何の役にも立たないと知るべきである。
*小賢しく立ち回ってもしょせんは釈迦の掌の上のようなもの。迂遠であっても、真っ当で正しい生き方が結局は自分を助けてくれる。
「世間の評判を鵜呑みにせず、自分で確認する」
*昨今の新聞やメディアが信頼に足りないのはなぜか?それは情報の考察が疎かで、報道姿勢が偏っているからだ。現代こそ、自分の眼で、耳で、肌で確かめることが重要であり、役に立つのだ。
2021年11月30日
菜根譚(11)

「部下の評価をあいまいにしない」
部下に対する評価をあいまいにしていると人はやる気を失う。その評価は公平公正を保たねばならない。もし評価に私情を交えるとと信用を失い、誰もついてこなくなる。
*人間は他人の評価が気になる生き物である。良い評価であっても悪い評価であっても、宙ぶらりんになっては相手も気をもむ。冷静に迅速に伝えることが肝要である。
「逃げ道を残してやる」
逃げ道を絶たれた者は、決死の覚悟を持ち捨て身で反撃するのが常であり、こちらも小さくない犠牲を伴うものだ。
*逃げ道を残すこと、とどめを刺さないことで自分の利益を失わないという冷静な状況判断が時には大事である。
「ゆったり構えて相手が変わるのを待つ」
物事を把握するために、ゆったり構え自然と明らかになるのを待つべき時がある。人を使うのも先ずはやらせてみて自発的に変わるのを待つ方がよい。
*体験・経験することで物事の捉え方が劇的に変わる時がある。時には状況が変わるのを待つことも重要である。
「昔からの友人と新鮮な気持ちで付き合う」
①昔からの友人とはいつも新鮮な気持ちで付き合うこと②秘事を扱うときは、尚一層、公明正大な態度で臨むこと③老人や現役を退いた人には思いやりを持つこと、が人付き合いの要である。
「人の苦しみを見過ごさない」
自分の苦しみはひたすら耐え忍ばなくてはならないが、しかし、他人の苦しみは見過ごすことなく助けることだ。