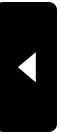2023年02月10日
正法眼蔵随聞記⑩

(正法眼蔵随聞記 四)
3・果報にも恵まれ家をも興す人は皆心が正直で人のためにも良くする人である。
このような人物が、理想的な篤志家であろう。
4・財宝を持っている人には怒りと辱めの二つの難がきっとくる。貧しく欲張らないならば身は安泰で心は束縛がない。
資産家は知らず知らず驕り高ぶってしまうことから災難を受けるのであろう。物欲から脱し、足るを知る精神的余裕の者こそ真に幸せなのである。
5・昇進や高い地位に就こうと思ったりすることを古人は恥とした。禅僧たるものはひたすら道を悟ろうということだけ考え、他に何事もあってはならない。
求道者は名利に淡恬としていなくては、道を究めることはできないものだ。
6・穏やかな言葉で改めさせたり、勧めたりしても従う者は従うものである。荒々しい言葉で人を憎んでりつけるのは全く禁止すべきである。
荒い言葉遣いで強制的に他人を指導しようとしても上手くいくわけがない。ましてや体罰などもってのほかである。
7・その人の徳を取り上げよ。欠点を取り上げてはならない。君子は徳を取って失を取らず。
他人に対しては短所には目をつむり長所を伸ばすことである。人間はその長ずる所にその人物の良さが凝縮されているのだ。
2023年02月09日
正法眼蔵随聞記⑨

16・在家の場合は孝経などに書かれていることを守って父母の生存中にお仕えする。死後にも報恩の行いをする。
親孝行は仏道修行なのである。
17・いつ死ぬかわからないという覚悟でひたむきに励み、さらに志を強くしてゆくならば悟りを得ないということはない。
・自分の命はたった今あるだけなのだ。
生を深く愛し、時間を無駄にするな。生命など儚く一瞬のものなのである。
20の(1)・大名・家老・侍・庶民に至るまで皆各々担当する仕事があり、それに従事するのを人らしい人という。これに背くのは天を乱すこととして天罰を受ける。
・むやみに自分自身を苦しめたり、できないことをせよ、とは仏の教えでは勧めることはない。
・昨日今日思いついた考えなどにはとらわれず、ひたすら仏の決まりに順うべきである。
与えられた職責を全うする者こそ天命に適った人物であり、それに背くと天命に反することになる。意図的に苦労を求めたり、不可能なことに無理やり挑むなど仏道にはない。ひたすら仏理に順うべきなのだ。
2023年02月08日
正法眼蔵随聞記⑧

10・世の名利を離れて一介の修行者となるということは、世人の不確かな分別判断を気に欠けないことである。
・人が見ていないから、知らないからと言って悪事をしてはならない。
俗世間の評価を気にしているようでは、真実を見つけることなどできやしない。
11・志をしっかり決め、全力を挙げて師について仏道を学ぶ人は悟りを得ないということはない。
・あてにならない世にいつまでも生き永らえていられると思い、様々な生活手段を考え、他人に対して悪事を企み、無駄に時を過ごすのは極めて愚かなことだ。
・(目的に対して)覚悟が出来たらそのあとはまことにたやすい。生まれつきの才能や利口さは全く問題ではない。
定めた目標に真摯に取り組み続ければ必ず達成でき、横道に逸れることがなければ無駄に時を過ごすことはなく、ひたすら取り組む覚悟さえあればそのほかの事は大した問題ではない。
12・多くの人が遁世しないのは自分の身を思わない、考えが深くない、優れた指導者に会わない、からである。
乱れた世にあっては、遁世しない人は珍しいのだろう。現代においては、市井の中にいながら目立たず出しゃばらずというのが遁世であろう。
2023年02月07日
正法眼蔵随聞記⑦

6・あなた方各々、一生の間に必要なものは生まれつき備わっている。余分に手に入れようとして走り回ってはいけない。
・探し求めないでも命を支えるだけのものは天然自然に備わっている。仮に奔走して財産を持ってみても今にも死がやってきたらどうするのか。
分不相応な財産、不要な能力、無用な肩書、等は蛇足であり淡雪のようなもので、死んだら残らない。足るを知るという生き方こそ大切である。
7・語録を見て何の役に立つのか?国に帰って人を導く為だ。それが何の役に立つのか?衆生に利益を与えるためだ。(それが)結局のところ何の役に立つのか?
・語録などを読んだりその内容を他人に教えるなどの事は、自分の修業のうえでも他人を導くうえでも不幸なことである。
語録などを参考にすること自体は悪とは思えない。要は読んでいる時に私欲に利用しようという心根が生じてきたらダメだということではないか?
8・本当は内に修めた徳も無いのに人から崇められてはならない。我が国の人は真に内徳を探り知ることができず、表に見える形だけで人を崇める。
我が国の人は表に見える形だけで崇める傾向があるので、崇められる側の人間が謙虚に自制かつ自省しないと有頂天になりやすいので注意せよ、という戒めである。
9・どんな悪人であっても真実の道を聞こうと真心から尋ねたならば、恨みを忘れてその人のためにこれを説くべきである。
・文章が整っていなくても、道理さえよく通じていれば仏道のためにも重要なことである。他の学問知識もこれと同様である。
善意・正道に目覚めた者に対して、過去の経緯など気にするべきではない。また、しっかりと要点を抑えているなら、形式など気にしないことだとも言っている。
2023年02月06日
正法眼蔵随聞記⑥

〈正法眼蔵随聞記 三〉
1・心を調え、その動きを押し静めてしまえば身を捨てることも世を捨てることもたやすいことである。
・悪事をせず善事を身を以って行ってゆくのが、身も心も捨てることになる。
物静かで落ち着いた精神状態でいられる境地が自在の境地である。善事=他者への奉仕、だから我欲を捨てなければできるものではない。
3・自分に仁徳があってしかも悪く言われるならば心配はいらない。仁徳もないのに誉められるならば自省せよ。
・道心はあるのに愚かな人々から非難されるのは気にする必要はない。他人から道心があるように見られていながら自分に道心がないことは自戒せよ。
事実とかけ離れた称賛は受け取ってはならず、自省・自戒しながら精進すべきなのだ。
4・世間の人は自分ひとり悟ろうとする小乗根性である。
・自分の心で良いと思い、又、世間の人が良いと思うことが必ずしも良いとは限らない。
前段は個人主義よりも全体主義ということか?良いか悪いかの判断は難しいということ。良い事とは多数決で決まるものではなく、その価値は不変である。
5・儒者は元々身を忘れて、幼いころから成人するまで学問を本務としている。儒者でない普通の人は自分の勤めや交際を第一として片手間に学問をする。
普通の人は学問が本分ではないから少なからず片手間になってしまうが、それでも学問に時間を割くだけ素晴らしいことだと思う。
自分の勤めや交際を第一としても、何ら恥じることはない。