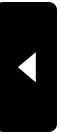2023年03月16日
言志四録⑭

「まだ来もしない将来を迎えることは出来ないし、過ぎ去った過去を追いかけても追いつかない。」
「逆境にあっても不満ややけを起こさず、順境にあっても慢心や怠け心を起こしてはならない。」
「貧富は天の定めるところであるから、各人はその立場・環境に安んじて最善を尽くせばよい。」
「心が穏やかなことが最高の幸せである。」
「学問に対してはどこまでも突き進んで満足してはならない。」
「艱難辛苦を経験すると、考えが自然と深く細やかになり何事もよく成就する。」
2023年03月15日
言志四録⑬

「大臣の地位にある者は天下の事情に通じ、物事を処理するにあたっては公明正大でなければならない。事情に通じていなければ一方に偏ってしまうし、公明正大でなければ頑固になってしまう。」
「人情が自分に向かうか背くかは敬と慢の違いにある。」
「恩や怨は小さなことから起こるものだから、十分に考慮して行動を慎むべきである。」
「正義と知恵とから(導き出される)思い切った断行・果断は最良である。」
「いったん、悔い悟った者へは、以前の悪い事を追及してはならない。」
「一人でいるときの修養は、、大勢の集まりの中にいるような気持でいればよい。人との応対の修養は、一人で閑静な住まいにいるのと同じ気持ちでいればよい。」
2023年03月14日
言志四録⑫

「人は無我の境地になれば我が身を忘れる。あるのは正義のみ。物欲が無ければ眼中人無し。あるのは勇気のみ。」
「味方を知ることは易しいようで難しい。」
「戦いにおいては武器に依存するな。人の和を頼りにすべきである。また軍勢が多いか少ないかは問題ではない。軍律が保たれているかどうかに注意しなければならない。」
・組織は、整理整頓→挨拶→人の和 、の順で乱れてゆくものである。
「全軍の調和がとれていなければ戦うことは出来ない。役人全体がまとまっていなければ良い政治など出来ない。」
「才能があっても度量が無ければ人を包容できない。度量があっても才能が無ければ事を成就できない。才能と度量と二つを兼ね備えることが出来ないなら、才能を捨てて度量のある人物になれ。」
・才能は、自分になければ人の能力を借りれば事足りる。
2023年03月13日
言志四録⑪

《Ⅲ 言志晩録》
「心は常に平静であることが肝要である。平静であれば心も安定する。気は安らかであることが大事である。気が安らかであれば何事も率直に行うことが出来る。」
「濁った水もまた水であり、澄めば清水となる。カラ元気も元気のうちであり、一転すれば正大な気になる。」
「耳慣れた意見ばかりを好しとして、(自分と)異なる意見を嫌ってはいけない。」
「疑うことは悟りを得る機会である。」
「学問にも終わりが無い」
「少年の時に学んでおけば壮年になってから役に立ち、何事かを為せる。壮年の時に学んでおけば老年になっても気力が衰えない。老年になっても学び続ければ見識がさらに高まり、社会に貢献できて名を残す。」
・学問をすることは生涯の宝となる。
「人を見るときは必ずその人の優れたところ(のみ)を見るべきで、短所を見てはいけない。」
「仕事をする時は十分に準備をして事に当たれば失敗することはない。」
2023年03月10日
言志四録⑩

「ゆったりとした気持ちで世の中に逆らわないのが和である。また、自分の立場を正しく守り、世俗の欲望に惑わないのが介である。」
「名誉や利益は元々(絶対的に)悪いものではないが、私物化してはならない。」
「知(知識・知恵)は行(行動)をコントロールする天道である。」
「軽率でも怠け者でもない人が、よく事態を収拾し事を成就させることが出来る。」
「学問するからには本を読むにしても納得するまで読むことである。行間を読むように心掛ければ字面だけでは分からないことも納得できるものだ。」
「浮かれた心(心理状態)や騒がしい心(心理状態)で(本を)読んではいけない。」
「真実の言葉は人を感動させる。」
「敬忠、寛厚、信義、公平、廉清、謙抑、は上に立つ者の誰もが戒めとすべきである。」
「老人が(新たな)勉学に取り組む場合、益々志気を励まして、青年や壮年の人に負けてはならぬ、という気概が必須である。老人にはもう取り返すだけの明日はない(時を無駄に出来ない)。今日学ばずして、明日があると考えてはいけない。」