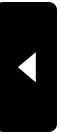2024年12月10日
荘子⑪

(無用と有用)
「自らの長所が自らの生命を縮めている。凡そこの世の人も物もみな有用であろうとして同じ愚を繰り返している。」
「お前(大工)も私(老木)もいずれも自然界の一物に過ぎない。 物 が 物 の価値付けをしてどうなるというのだ?」
2024年12月09日
荘子⑩

「宿命と社会的規範の二つから人は逃れられぬ。人の力ではどうにもならないことは虚心に受け入れることが至高の徳である。」
「はじめは慎重でもいつしか粗雑になるのが常である。始めは簡単でもいつしか抜き差しならなくなるのが物事の常である。」
2024年12月08日
荘子⑨

「道の前に小さな自己など存在しない。」
「世俗に同化して、しかも世俗に居ることを忘れてしまえ。」
「人為に頼る者は作為を離れることは出来ない。逆に天に従い自然に身を委ねるならば作為の跡は残らない。」
「知あるが故、人は知を恃む。しかし、知を捨ててこそ真の知を得る。」
「外界の事象は耳目の捉えるまま受け入れよ。知で測ろうとするな。」
2024年12月07日
荘子⑧

(養生主)
「善悪にとらわれず、自然に則り、自然のままに生きることで、天寿を全うし安らかで充実した生涯を送ることが出来る。」
(人間世)
(無心の境地)
「人間がなぜ徳を失い知に頼ることになったのか?徳を失ったのは名誉欲に捉われたからだし、知に頼るようになったのは争いに必要だからである。」
「一切の迷いを去り、心を純一に保て。耳は音を感覚的に捉えるにすぎず、心は事象を知覚するにすぎない。」
「気で聴くとはあらゆる事象をあるがままに無心に受け入れることなのだ。」
2024年12月06日
荘子⑦

「聖人は一切の現象をあるがままに任せて論じようとしない。人間社会について論じても評価は加えない。事実を述べるだけで是非を云々しようとはしない。」
「言葉を絶対視し是非を論じるのは道を理解していない証拠である。」
「道は道と判断された時道ではなくなる。言葉(概念)は成立した時事物の実相から離れる。愛は特定の対象に留まる(執着する)時愛ではなくなる。廉潔は意識的に行われれば偽りになる。勇を恃んで人と争う時勇は勇でなくなる。」
「人間にとって最高の知とは、知の限界を悟ることである。」