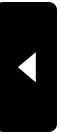2019年06月28日
女子ワールドカップ フランス なでしこジャパンの評価
あの組み合わせなら、ベスト4進出の可能性も有りましたが、残念ながらベスト16で散ったなでしこジャパン。
大会の4試合を振り返りつつ、来年のオリンピックまでの強化について考えてみる。

【グループリーグ第1戦 なでしこ 0 (前半0-0) 0 アルゼンチン女子代表】
初戦と言う事で硬くなったのだろうが、守備の意識は高かったのだが運動量とダイレクトプレイというなでしこのストロングポイントが表現できていなかった。
また、シュート意識の低さは落第点に等しい。ただボールを回しているだけで工夫のかけらも無く、いわば無気力試合のようなものであった。
もっとシンプルにゴールを狙っても良かったと思う。また、ハーフタイムでの指示や選手交代も含め、ゲーム中に対応を示せず、高倉監督の無策ぶりもあらためて露呈してしまった。このやり方では残りの2試合もこの時点では不安しかなかった。

【グループリーグ第2戦 なでしこ 2 (前半2-0) 1 スコットランド女子代表】
初戦とはうってかわって、入りからこぼれ球へのリアクションが早くて強く、いい感じであった。
前半は素早いダイレクトプレイの場面と落ち着いてスローに展開する場面がメリハリが利いていて、それがスコアに現れていた。
岩渕の得点はまさにスーパーゴールと言える。
杉田・三浦のボランチコンビはバランスがいいし、試合毎に連携が飛躍的に向上しているし、これなら阪口に頼らずとも充分戦える。又、GK山下のボール扱いと安定感は安心して見ていられた。
感じたのは、なでしこの心臓部はやはりボランチと両サイドバックである。また、CBはフィジカルの強さよりスピードとボールテクニックに優れる点が必要だと思う。
その点からすると、市瀬のミスからの失点は代表レベルでは有り得ないもので、いただけないね。
結局なでしこは運動量と粘り強さが生命線ということを再確認した。

【グループリーグ第3戦 なでしこ 0 (前半0-1) 2 イングランド女子代表】
結果は残念なものであったが、ノックアウトステージに向けて良いトレーニングになったのではないか?決定力と守備陣のラストピース(熊谷の代役または相棒のCB)が見つかれば、世界のベスト4には充分君臨できるし、アメリカ・ドイツと常に伍していける感触を感じた。
ダイレクトパスを3本続けられたら、いまのなでしこのレベルならば決定機を作れる。ミスを恐れずやり切れるかどうか?ミスしても取り返したらいいんだし、ミスを繰り返さなければ問題ないのだ。
スコアは0-2であるが、局面局面を観察すると、フィジカルとパワーで及ばなくても、高精度のボールテクニックがあれば相手を凌駕できるのが良く分かる試合であった。
ただ、少々苦言を呈すると、リードされているのに凌ぐだけの逃げ切り型の守備では意味をなさない。得点する為に相手からボールを奪うという攻撃型の守備でなくてはならない。また、決定力不足は深刻で、惜しい!では意味がないと思う。

【ラウンド16 なでしこ 1 (前半1-1) 2 オランダ女子代表】
ちょっとショックな負け方であって、非常に悔いの残る敗戦だと思う。
1失点目はしっかりやられていたものであるから、ある程度仕方ないが、2失点目のPKは自分はミスジャッジではないかと思う。試合を通じて、レフェリングには疑問符が付くものが多かった。
試合を通じて、なでしこのストロングポイントは充分出せていたし、深い位置からの丁寧なボール回し・ビルドアップもキッチリ出来ていた。
惜しいシュートも多かったし、内容ではオランダを圧倒していたと思う。
しかし、決めるときに決めないと、このような敗戦になるのはサッカーの常。なでしこの決定力と言う点は改善の余地が大いにある。また、シュート意識も男子同様の課題だと思う。もっと泥臭くゴールに迫ってもいいんじゃないかな?
オリンピックまで時間はないが、女子サッカー界全体のレベルアップは急務。アンダー年代のボールテクニックに長け、スピードのあるプレイヤーをもっと伸ばせば、東京オリンピックのメダル獲得は充分可能だと思う。
高倉監督ではこのあたりが限界なので、人選も含めて早急に協会は考えなくてはならないのではないかと思う。
大会の4試合を振り返りつつ、来年のオリンピックまでの強化について考えてみる。

【グループリーグ第1戦 なでしこ 0 (前半0-0) 0 アルゼンチン女子代表】
初戦と言う事で硬くなったのだろうが、守備の意識は高かったのだが運動量とダイレクトプレイというなでしこのストロングポイントが表現できていなかった。
また、シュート意識の低さは落第点に等しい。ただボールを回しているだけで工夫のかけらも無く、いわば無気力試合のようなものであった。
もっとシンプルにゴールを狙っても良かったと思う。また、ハーフタイムでの指示や選手交代も含め、ゲーム中に対応を示せず、高倉監督の無策ぶりもあらためて露呈してしまった。このやり方では残りの2試合もこの時点では不安しかなかった。

【グループリーグ第2戦 なでしこ 2 (前半2-0) 1 スコットランド女子代表】
初戦とはうってかわって、入りからこぼれ球へのリアクションが早くて強く、いい感じであった。
前半は素早いダイレクトプレイの場面と落ち着いてスローに展開する場面がメリハリが利いていて、それがスコアに現れていた。
岩渕の得点はまさにスーパーゴールと言える。
杉田・三浦のボランチコンビはバランスがいいし、試合毎に連携が飛躍的に向上しているし、これなら阪口に頼らずとも充分戦える。又、GK山下のボール扱いと安定感は安心して見ていられた。
感じたのは、なでしこの心臓部はやはりボランチと両サイドバックである。また、CBはフィジカルの強さよりスピードとボールテクニックに優れる点が必要だと思う。
その点からすると、市瀬のミスからの失点は代表レベルでは有り得ないもので、いただけないね。
結局なでしこは運動量と粘り強さが生命線ということを再確認した。

【グループリーグ第3戦 なでしこ 0 (前半0-1) 2 イングランド女子代表】
結果は残念なものであったが、ノックアウトステージに向けて良いトレーニングになったのではないか?決定力と守備陣のラストピース(熊谷の代役または相棒のCB)が見つかれば、世界のベスト4には充分君臨できるし、アメリカ・ドイツと常に伍していける感触を感じた。
ダイレクトパスを3本続けられたら、いまのなでしこのレベルならば決定機を作れる。ミスを恐れずやり切れるかどうか?ミスしても取り返したらいいんだし、ミスを繰り返さなければ問題ないのだ。
スコアは0-2であるが、局面局面を観察すると、フィジカルとパワーで及ばなくても、高精度のボールテクニックがあれば相手を凌駕できるのが良く分かる試合であった。
ただ、少々苦言を呈すると、リードされているのに凌ぐだけの逃げ切り型の守備では意味をなさない。得点する為に相手からボールを奪うという攻撃型の守備でなくてはならない。また、決定力不足は深刻で、惜しい!では意味がないと思う。

【ラウンド16 なでしこ 1 (前半1-1) 2 オランダ女子代表】
ちょっとショックな負け方であって、非常に悔いの残る敗戦だと思う。
1失点目はしっかりやられていたものであるから、ある程度仕方ないが、2失点目のPKは自分はミスジャッジではないかと思う。試合を通じて、レフェリングには疑問符が付くものが多かった。
試合を通じて、なでしこのストロングポイントは充分出せていたし、深い位置からの丁寧なボール回し・ビルドアップもキッチリ出来ていた。
惜しいシュートも多かったし、内容ではオランダを圧倒していたと思う。
しかし、決めるときに決めないと、このような敗戦になるのはサッカーの常。なでしこの決定力と言う点は改善の余地が大いにある。また、シュート意識も男子同様の課題だと思う。もっと泥臭くゴールに迫ってもいいんじゃないかな?
オリンピックまで時間はないが、女子サッカー界全体のレベルアップは急務。アンダー年代のボールテクニックに長け、スピードのあるプレイヤーをもっと伸ばせば、東京オリンピックのメダル獲得は充分可能だと思う。
高倉監督ではこのあたりが限界なので、人選も含めて早急に協会は考えなくてはならないのではないかと思う。
2019年06月27日
森保J、コパアメリカ参戦で得たもの
アジアカップでファイナリストになった事による、コパアメリカへの招待参加。
GLの組み合わせを見たときは、トルシエ時代のように惨敗に終わるであろうと感じていた。
しかしながら、次回ワールドカップ予選や来年のオリンピックに向けて、本気モードの南米勢と対戦する事は高い金払って欧州の強豪と親善試合を組むよりも、費用対効果の面ではるかに良いと思っていた。
その通りに、たった3試合であったが非常に良い強化となったのではと感じている。
では、各試合を振り返ってみる。

【第1戦 森保J 0 (前半 0-1) 4 チリ代表】
一見、単なる惨敗(スコア上は実際そうなのだが)に見えるが、日本が先制さえしていたら、かえって守備が引き締まり、精神的にも乗ってきてプレスの強度が高まりいい試合になったのではないかと感じる。
ただし、もっとクレバーに、もっと勤勉に、もっと連動していかないと、この状態のままだと百戦百敗だろう。また、経験の浅い、若いプレーヤーはもっと気持ちをギラつかせて相手を「喰らってやる!!!」ぐらいの狂気が欲しい。
ま、久保はもちろんのこと、GK大迫、FW前田はフル代表レベルに達しているとの印象を受けましたが。
結局、『ジャイアントキリング』を引き起こすには充分な研究としっかりした作戦、クレイジーな運動量しかない。あとはパスミスをしないこととペナルティエリアに侵入して勝負する回数をもっともっと増やす事だ。

【第2戦 森保J 2 (前半 1-1 ) 2 ウルグアイ代表】
このグループ中、最強の相手にどれだけミス無くやれるか?(パス、トラップ、タッチ等)に注目していたが、試合を通じて及第点である。
まあギラつきみたいなものは特に感じなかったが、非常に落ち着いた試合をしていて、(特に若手に)インテリジェンスを感じた。ただ、欲を言えばシュートにスアレスが持っているような「危険性」を備えたいものだ。やっぱり、一瞬たりとも気が抜けない!と相手に思わせるようじゃないと決定力は上がらないのではないかな。
失点の場面に関わらず、判断が遅い&アバウトな局面がチョコチョコあり、それがピンチや劣勢を招いていた。このあたりはやはり真剣勝負を通じて経験しないと改善できないので、非常にいい経験になったと思う。
もう一つ感じたのは、柴崎のパートナーとなりうるボランチの発掘または育成が急務で、恐らくそれがゲームをコントロールしうるキーパーソンになり得るということ。まあ色々組み合わせを試す必要があろう。
この試合、解説の川勝さんが非常に落ち着いていて分かりやすかった。感情的にならず淡々と分析して話すのは解説のお手本だね。

【第3戦 森保J 1 (前半 1-1 ) 1 エクアドル代表】
グループステージ突破の懸かった両チームなだけに、試合の入りは非常に慎重であった。
エクアドルのスピード・プレー強度・サイド攻撃はかなり危険な質であったが、ただ、技術的な上手さというものはなかった。
日本は疲労からか動きが重く、こぼれ球を拾えていないし、空いているスペースを突ききれていない。逆にサイドバックの裏をしばしばとられていた。加えて距離感が悪くパスの連続性が良くなかったし、両サイドの効果的な攻撃参加も少なかった。こういうところが勝ちきれない原因ではないかと思う。
この試合に関して言えば、交代策も効果的でなかった印象。個人的には伊藤達哉を見たかった。また、岡崎は大迫頼みのワントップから脱却できうる可能性を示した点で、今後の代表の人選に幅を持たせてくれたと思う。
この試合に象徴されるように、日本はシュート意識をもっと強く持つことに加え、シュートのパワーアップについても即座に取り組むべき課題だと言える。
残念ながら、グループリーグ突破や南米の地での対南米勢初勝利はならなかったが、若い面々のみならず、招集された全員がこの大会で経験した事は今後に有益なものである事に間違いはない。更に、協会にとっても非常にプラスの経験となった事は疑いの余地はないだろう。
次の真剣勝負が早く観たいものである。
GLの組み合わせを見たときは、トルシエ時代のように惨敗に終わるであろうと感じていた。
しかしながら、次回ワールドカップ予選や来年のオリンピックに向けて、本気モードの南米勢と対戦する事は高い金払って欧州の強豪と親善試合を組むよりも、費用対効果の面ではるかに良いと思っていた。
その通りに、たった3試合であったが非常に良い強化となったのではと感じている。
では、各試合を振り返ってみる。

【第1戦 森保J 0 (前半 0-1) 4 チリ代表】
一見、単なる惨敗(スコア上は実際そうなのだが)に見えるが、日本が先制さえしていたら、かえって守備が引き締まり、精神的にも乗ってきてプレスの強度が高まりいい試合になったのではないかと感じる。
ただし、もっとクレバーに、もっと勤勉に、もっと連動していかないと、この状態のままだと百戦百敗だろう。また、経験の浅い、若いプレーヤーはもっと気持ちをギラつかせて相手を「喰らってやる!!!」ぐらいの狂気が欲しい。
ま、久保はもちろんのこと、GK大迫、FW前田はフル代表レベルに達しているとの印象を受けましたが。
結局、『ジャイアントキリング』を引き起こすには充分な研究としっかりした作戦、クレイジーな運動量しかない。あとはパスミスをしないこととペナルティエリアに侵入して勝負する回数をもっともっと増やす事だ。

【第2戦 森保J 2 (前半 1-1 ) 2 ウルグアイ代表】
このグループ中、最強の相手にどれだけミス無くやれるか?(パス、トラップ、タッチ等)に注目していたが、試合を通じて及第点である。
まあギラつきみたいなものは特に感じなかったが、非常に落ち着いた試合をしていて、(特に若手に)インテリジェンスを感じた。ただ、欲を言えばシュートにスアレスが持っているような「危険性」を備えたいものだ。やっぱり、一瞬たりとも気が抜けない!と相手に思わせるようじゃないと決定力は上がらないのではないかな。
失点の場面に関わらず、判断が遅い&アバウトな局面がチョコチョコあり、それがピンチや劣勢を招いていた。このあたりはやはり真剣勝負を通じて経験しないと改善できないので、非常にいい経験になったと思う。
もう一つ感じたのは、柴崎のパートナーとなりうるボランチの発掘または育成が急務で、恐らくそれがゲームをコントロールしうるキーパーソンになり得るということ。まあ色々組み合わせを試す必要があろう。
この試合、解説の川勝さんが非常に落ち着いていて分かりやすかった。感情的にならず淡々と分析して話すのは解説のお手本だね。

【第3戦 森保J 1 (前半 1-1 ) 1 エクアドル代表】
グループステージ突破の懸かった両チームなだけに、試合の入りは非常に慎重であった。
エクアドルのスピード・プレー強度・サイド攻撃はかなり危険な質であったが、ただ、技術的な上手さというものはなかった。
日本は疲労からか動きが重く、こぼれ球を拾えていないし、空いているスペースを突ききれていない。逆にサイドバックの裏をしばしばとられていた。加えて距離感が悪くパスの連続性が良くなかったし、両サイドの効果的な攻撃参加も少なかった。こういうところが勝ちきれない原因ではないかと思う。
この試合に関して言えば、交代策も効果的でなかった印象。個人的には伊藤達哉を見たかった。また、岡崎は大迫頼みのワントップから脱却できうる可能性を示した点で、今後の代表の人選に幅を持たせてくれたと思う。
この試合に象徴されるように、日本はシュート意識をもっと強く持つことに加え、シュートのパワーアップについても即座に取り組むべき課題だと言える。
残念ながら、グループリーグ突破や南米の地での対南米勢初勝利はならなかったが、若い面々のみならず、招集された全員がこの大会で経験した事は今後に有益なものである事に間違いはない。更に、協会にとっても非常にプラスの経験となった事は疑いの余地はないだろう。
次の真剣勝負が早く観たいものである。
2019年03月27日
キリンチャレンジカップ観戦記
キリンチャレンジカップ
3月22日 日本代表 0 (前半0-0) 1 コロンビア代表
3月26日 日本代表 1 (前半0-0) 0 ボリビア代表

アジアカップ以後、初の代表戦となるキリンチャレンジカップ2試合、相変わらずテレビ観戦です。
まずはコロンビア戦。
クアドラードが居ない位でほぼベストの布陣ではなかったか?というもの。
やはり簡単にいく相手ではありませんでした、だからこそ戦力の強化・発掘・育成という点では願ってもない強豪でした。
一番の好印象は鈴木武蔵。J1で結果も出せてて乗ってるという勢いのままに、フィジカルの強さも備えたスピードのあるセンターフォワードというように思えました。
久々の香川もコンビネーションもまずまずで、自分の良さも出しながら回りも良く見えており、何度か好パスを供給していました。
小林もこれまで呼ばれなかったのが不思議なくらい馴染んでいたし、有効でした。
柴崎にしても、この状態でなんでクラブで出れないのか不思議なくらい。動きもゲームコントロールも申し分なかったですし、良い出来だったと思います。
失点のPKは仕方有りませんね。でもまあ、こうゆう強くてしたたかなチームと試合してDFの個人能力を鍛える事は大切だと思います。
未体験よりは体験しておいたほうが絶対に良い。(特に南米勢は前線の個の力が際立っているし)
一度体験していれば次回の対応もしっかりイメージできますしね。
とにかく躍動し続けた90分間、ホームゲームなので無得点は少々不満が有るが、ホイッスルまで前向きなプレーをやりきった点は評価できます。
ただ、高さのある相手をどう攻略するかのアイデアと、崩しきる前でも強引にゴールへ向かう場面・個性がもっと有っても良いと思いました。
次はボリビア戦。
はっきりいってボリビアは弱くない、ということ。多少、技術に粗さがあるというだけで、カウンターの切れ味、鉄壁のDF、フィジカルの強靭さ、と眼を見張る場面は多かったです。
そのような相手にしっかり勝てた事は重要だと思いますね。
ただ鎌田については、このチームが彼を生かしきれていないと感じます。印象としては2トップの一角がフィットするのではないでしょうか?相方は武藤や川又、なんなら鈴木武蔵でもいいと思う。
香川・乾・宇佐美のセットは、足元ばかりでボールを貰いすぎるきらいはあったけれども、関係性としてはまずまずだったかなと思います。
小林は、いいサイドチェンジを何回か見せてくれましたがもっと長いボールを相手の裏のスペースに供給しても面白かったかもしれませんね。
橋本と西は、招集の期待に充分応え、役割を果たせていましたしフィットもしていたなと。安西は南米勢相手だとちょっと守備力に難ありかなと感じました。シュミットダニエルは及第点でしょう。
得点のシーンは中島が見事!欲を言えばその後の南野の決定的シーンはキッチリ決めておきたかったですけどね(笑)
森保さんの、『招集した選手をほぼ全員試合で試す』というスタイルは、自分の考えとしては目先の結果にとらわれすぎずに、真の意味での強化をようやく実践しつつあるなと.....。協会の方針も有るのかもしれませんが、良い傾向だと思います。
又、欧州勢よりは南米勢・中東勢という比較的日本の苦手な相手と多く強化試合を組んだほうが(移動の問題はあるにせよ)コスト的にも実効的にも良いのでは?と思えた2戦でした。
国内組は、リーグ戦やACLを通じてしっかり鍛錬し、結果を残せば代表に呼ばれるというモチベーションが上がったでしょうし、海外組もクラブでしっかりと結果を残せば代表入りも夢ではないということで、選手のモチベーション向上にも繋がった試合であったと思います。
南米選手権も楽しみですね。
3月22日 日本代表 0 (前半0-0) 1 コロンビア代表
3月26日 日本代表 1 (前半0-0) 0 ボリビア代表

アジアカップ以後、初の代表戦となるキリンチャレンジカップ2試合、相変わらずテレビ観戦です。
まずはコロンビア戦。
クアドラードが居ない位でほぼベストの布陣ではなかったか?というもの。
やはり簡単にいく相手ではありませんでした、だからこそ戦力の強化・発掘・育成という点では願ってもない強豪でした。
一番の好印象は鈴木武蔵。J1で結果も出せてて乗ってるという勢いのままに、フィジカルの強さも備えたスピードのあるセンターフォワードというように思えました。
久々の香川もコンビネーションもまずまずで、自分の良さも出しながら回りも良く見えており、何度か好パスを供給していました。
小林もこれまで呼ばれなかったのが不思議なくらい馴染んでいたし、有効でした。
柴崎にしても、この状態でなんでクラブで出れないのか不思議なくらい。動きもゲームコントロールも申し分なかったですし、良い出来だったと思います。
失点のPKは仕方有りませんね。でもまあ、こうゆう強くてしたたかなチームと試合してDFの個人能力を鍛える事は大切だと思います。
未体験よりは体験しておいたほうが絶対に良い。(特に南米勢は前線の個の力が際立っているし)
一度体験していれば次回の対応もしっかりイメージできますしね。
とにかく躍動し続けた90分間、ホームゲームなので無得点は少々不満が有るが、ホイッスルまで前向きなプレーをやりきった点は評価できます。
ただ、高さのある相手をどう攻略するかのアイデアと、崩しきる前でも強引にゴールへ向かう場面・個性がもっと有っても良いと思いました。
次はボリビア戦。
はっきりいってボリビアは弱くない、ということ。多少、技術に粗さがあるというだけで、カウンターの切れ味、鉄壁のDF、フィジカルの強靭さ、と眼を見張る場面は多かったです。
そのような相手にしっかり勝てた事は重要だと思いますね。
ただ鎌田については、このチームが彼を生かしきれていないと感じます。印象としては2トップの一角がフィットするのではないでしょうか?相方は武藤や川又、なんなら鈴木武蔵でもいいと思う。
香川・乾・宇佐美のセットは、足元ばかりでボールを貰いすぎるきらいはあったけれども、関係性としてはまずまずだったかなと思います。
小林は、いいサイドチェンジを何回か見せてくれましたがもっと長いボールを相手の裏のスペースに供給しても面白かったかもしれませんね。
橋本と西は、招集の期待に充分応え、役割を果たせていましたしフィットもしていたなと。安西は南米勢相手だとちょっと守備力に難ありかなと感じました。シュミットダニエルは及第点でしょう。
得点のシーンは中島が見事!欲を言えばその後の南野の決定的シーンはキッチリ決めておきたかったですけどね(笑)
森保さんの、『招集した選手をほぼ全員試合で試す』というスタイルは、自分の考えとしては目先の結果にとらわれすぎずに、真の意味での強化をようやく実践しつつあるなと.....。協会の方針も有るのかもしれませんが、良い傾向だと思います。
又、欧州勢よりは南米勢・中東勢という比較的日本の苦手な相手と多く強化試合を組んだほうが(移動の問題はあるにせよ)コスト的にも実効的にも良いのでは?と思えた2戦でした。
国内組は、リーグ戦やACLを通じてしっかり鍛錬し、結果を残せば代表に呼ばれるというモチベーションが上がったでしょうし、海外組もクラブでしっかりと結果を残せば代表入りも夢ではないということで、選手のモチベーション向上にも繋がった試合であったと思います。
南米選手権も楽しみですね。
2019年02月03日
悔しいですよね
アジアカップ2019 決勝 日本代表 1 (前半 0-2 ) 3 カタール代表
まだまだ発展途上の森保ジャパン。
なんだかんだ浮き沈みはあってもどうにか決勝まで辿り着いたアジアカップ2019・ファイナルでしたけど、準優勝でした。
出来たら頂点に立って無敗記録を伸ばして欲しかったですけど、それでもこの後のキリンチャレンジカップやコパアメリカに向けて一度頭を冷やすという意味で、負けておいてもいい材料になるのかも知れません。
決勝までの全7戦を見て感じた事と、決勝の戦評を述べてみたい思います。
まず、大会全体を通して、チームのコンセプトが着実に見えてきたという事。
これは非常に期待を抱かせる好材料だと思います。
現行のシステムの中で、各ポジションに求められるスキルとパーソナリティを明確にし、更にプレイヤーのインテリジェンスを重視するというのが監督の考えのように感じられました。
その中で、冨安・遠藤という新世代プレーヤーの台頭は最も喜ばしいですね。また、武藤も非常にキレがあって良かった。
採用しているシステム的に、大迫に先発を譲った感はありますが、2トップとか3トップなら物凄く強力なプレイヤーになるのではないでしょうか。GKのシュミット・ダニエルも1試合とはいえ、経験を積めたことは将来に向けて良い布石になると思う。
勿論、南野・堂安は大会を通じてよかったと思いますし、原口もまだまだ発展できる印象でした。
二つ目は、プレースキックの種類の少なさと、長距離シューター不在の不安です。
確かに、今回のチームでは、プレースキックは柴崎が最も適任ではありました。しかし、CK・FKのキックの質が基本的に単調で、例えば、中村俊輔のような多彩なキックが蹴れるわけではない。
大会を通じて、プレースキックが得点に繋がったのは冨安の1ゴールだけでは、代表の武器とは言えないでしょう。
また、過去の代表.....少なくともザックジャパンの全盛期までは複数のプレースキッカーが居ました。本田圭祐と遠藤保仁、中村俊輔と小野伸二、名波浩と中田英寿など、スペシャリストが複数在籍していたものです。
それ以外でも、往年のFKの名手といえば、木村和司、岩本輝雄、澤登正朗、三浦淳寛、阿部勇樹、小笠原満男、中田浩二など、その時代に強烈な印象を残した選手が数多くいました。
直接も狙えるし、いろんなパターンもあるし、という相手にプレッシャーになるようなキッカーに柴崎がなるのか、それとも他に見出すのか分かりませんが、もうツーランクぐらいレベルアップの余地はあると感じました。
長距離シューターの不在も不安材料の一つです。特にボランチのシュート意識が低い気がします。
長谷部、山口蛍、遠藤保仁などはここぞという場面でシュートをしっかり打っていたものですが、今大会・現代表においては殆ど見当たりませんね。
全線の3~4人しかシュートを打たないのであれば、相手DFはとても守りやすいでしょうし、対策が立てやすいものです。30m以上のレンジから強烈なシュートを放つプレーヤーが居れば、非常に重宝すると思いますし、ボランチだけでなくサイドバックもシュート意識を持ってプレーすれば攻撃が多彩になるはずです。是非とも発掘を切望します。
三つ目は、やはりダイレクトプレイとハードワークが日本の生命線ということでしょう。
会心のゲームだった準決勝のイラン戦、リズム良くダイレクトプレイが連続した事で相手にストレスを与え続け、ハードワークを90分やりきった事で局面でのデュエルに悉く勝利し、試合の流れを自分たちに引き寄せて完勝しました。
なでしこにも言える事ですが、現在の日本代表の立ち位置は決して強豪国というものではなく、まだまだ発展途上でありレベルアップの余地は大いにありますが、格上の相手を如何にして倒すか?を考えた場合やはりダイレクトプレイとハードワークで、ワンチャンスをものにし相手にストレスを与え続けてペースを乱す事しかない。
それこそコパアメリカは軒並み格上の、しかも日本が苦手な南米勢が相手ですから良い強化になると思いますね。是非とも好試合を演じ、効果的な強化に繋げてもらいたいですね。
さて、決勝戦の戦評。
まずはなりふり構わぬカタールの【急造強化】に日本も含めて他の各国チームが飲み込まれてしまって終わった感が強いですね。
W杯開催を控えたカタールという津波に、訳も分からぬまま押し流されてしまったというところでしょうか。
確かに、カタールのシュート意識の高さと強引さ、プレースピードは脅威でしたが、日本も後半のPK献上までは逆転の勢いが濃厚であり、勝負のアヤというものはほんのわずかの箇所にあるものだと痛感されられました。
たられば、はナンセンスでしょうけど、やっぱり遠藤航の欠場が痛かった。代役の塩谷が悪いという事ではなく、柴崎との連携において一日の長が有り、攻撃へのスイッチとカウンターの芽を摘む役割を十二分にこなしてきたプレーヤーを失った事は最大のハンディであったと言わざるを得ません。
また、中島の不在も大きかったか?トップ下を担った南野は充分に評価に値しますが、攻撃のバリエーションと意外性という面で、現在の日本代表にとって中島のタレントは必要不可欠であり、彼を欠いた事で柴崎のゲームコントロールの固さが顕著になってしまった感はある。
やはりトップ下というポジションは日本にとって必要であり、中島の他、香川、清武の復活も期待したいですし、大島の成長にも希望を見出したいものです。
今回、悔しい結果に終わりましたが、大迫不在の場合のシステムという課題が見つかりましたし、若手の底上げも出来ました。
まだ未招集の海外組、埋もれているが今シーズン台頭期待の国内組、ルーキー、と選択肢は少なくないと思います。
はっきりいって『1軍半』的な側面もあった今回の代表、まだかなりの伸びしろがあると睨んでいます。
まずはコパアメリカでいいゲームを!
まだまだ発展途上の森保ジャパン。
なんだかんだ浮き沈みはあってもどうにか決勝まで辿り着いたアジアカップ2019・ファイナルでしたけど、準優勝でした。
出来たら頂点に立って無敗記録を伸ばして欲しかったですけど、それでもこの後のキリンチャレンジカップやコパアメリカに向けて一度頭を冷やすという意味で、負けておいてもいい材料になるのかも知れません。
決勝までの全7戦を見て感じた事と、決勝の戦評を述べてみたい思います。
まず、大会全体を通して、チームのコンセプトが着実に見えてきたという事。
これは非常に期待を抱かせる好材料だと思います。
現行のシステムの中で、各ポジションに求められるスキルとパーソナリティを明確にし、更にプレイヤーのインテリジェンスを重視するというのが監督の考えのように感じられました。
その中で、冨安・遠藤という新世代プレーヤーの台頭は最も喜ばしいですね。また、武藤も非常にキレがあって良かった。
採用しているシステム的に、大迫に先発を譲った感はありますが、2トップとか3トップなら物凄く強力なプレイヤーになるのではないでしょうか。GKのシュミット・ダニエルも1試合とはいえ、経験を積めたことは将来に向けて良い布石になると思う。
勿論、南野・堂安は大会を通じてよかったと思いますし、原口もまだまだ発展できる印象でした。
二つ目は、プレースキックの種類の少なさと、長距離シューター不在の不安です。
確かに、今回のチームでは、プレースキックは柴崎が最も適任ではありました。しかし、CK・FKのキックの質が基本的に単調で、例えば、中村俊輔のような多彩なキックが蹴れるわけではない。
大会を通じて、プレースキックが得点に繋がったのは冨安の1ゴールだけでは、代表の武器とは言えないでしょう。
また、過去の代表.....少なくともザックジャパンの全盛期までは複数のプレースキッカーが居ました。本田圭祐と遠藤保仁、中村俊輔と小野伸二、名波浩と中田英寿など、スペシャリストが複数在籍していたものです。
それ以外でも、往年のFKの名手といえば、木村和司、岩本輝雄、澤登正朗、三浦淳寛、阿部勇樹、小笠原満男、中田浩二など、その時代に強烈な印象を残した選手が数多くいました。
直接も狙えるし、いろんなパターンもあるし、という相手にプレッシャーになるようなキッカーに柴崎がなるのか、それとも他に見出すのか分かりませんが、もうツーランクぐらいレベルアップの余地はあると感じました。
長距離シューターの不在も不安材料の一つです。特にボランチのシュート意識が低い気がします。
長谷部、山口蛍、遠藤保仁などはここぞという場面でシュートをしっかり打っていたものですが、今大会・現代表においては殆ど見当たりませんね。
全線の3~4人しかシュートを打たないのであれば、相手DFはとても守りやすいでしょうし、対策が立てやすいものです。30m以上のレンジから強烈なシュートを放つプレーヤーが居れば、非常に重宝すると思いますし、ボランチだけでなくサイドバックもシュート意識を持ってプレーすれば攻撃が多彩になるはずです。是非とも発掘を切望します。
三つ目は、やはりダイレクトプレイとハードワークが日本の生命線ということでしょう。
会心のゲームだった準決勝のイラン戦、リズム良くダイレクトプレイが連続した事で相手にストレスを与え続け、ハードワークを90分やりきった事で局面でのデュエルに悉く勝利し、試合の流れを自分たちに引き寄せて完勝しました。
なでしこにも言える事ですが、現在の日本代表の立ち位置は決して強豪国というものではなく、まだまだ発展途上でありレベルアップの余地は大いにありますが、格上の相手を如何にして倒すか?を考えた場合やはりダイレクトプレイとハードワークで、ワンチャンスをものにし相手にストレスを与え続けてペースを乱す事しかない。
それこそコパアメリカは軒並み格上の、しかも日本が苦手な南米勢が相手ですから良い強化になると思いますね。是非とも好試合を演じ、効果的な強化に繋げてもらいたいですね。
さて、決勝戦の戦評。
まずはなりふり構わぬカタールの【急造強化】に日本も含めて他の各国チームが飲み込まれてしまって終わった感が強いですね。
W杯開催を控えたカタールという津波に、訳も分からぬまま押し流されてしまったというところでしょうか。
確かに、カタールのシュート意識の高さと強引さ、プレースピードは脅威でしたが、日本も後半のPK献上までは逆転の勢いが濃厚であり、勝負のアヤというものはほんのわずかの箇所にあるものだと痛感されられました。
たられば、はナンセンスでしょうけど、やっぱり遠藤航の欠場が痛かった。代役の塩谷が悪いという事ではなく、柴崎との連携において一日の長が有り、攻撃へのスイッチとカウンターの芽を摘む役割を十二分にこなしてきたプレーヤーを失った事は最大のハンディであったと言わざるを得ません。
また、中島の不在も大きかったか?トップ下を担った南野は充分に評価に値しますが、攻撃のバリエーションと意外性という面で、現在の日本代表にとって中島のタレントは必要不可欠であり、彼を欠いた事で柴崎のゲームコントロールの固さが顕著になってしまった感はある。
やはりトップ下というポジションは日本にとって必要であり、中島の他、香川、清武の復活も期待したいですし、大島の成長にも希望を見出したいものです。
今回、悔しい結果に終わりましたが、大迫不在の場合のシステムという課題が見つかりましたし、若手の底上げも出来ました。
まだ未招集の海外組、埋もれているが今シーズン台頭期待の国内組、ルーキー、と選択肢は少なくないと思います。
はっきりいって『1軍半』的な側面もあった今回の代表、まだかなりの伸びしろがあると睨んでいます。
まずはコパアメリカでいいゲームを!
2019年01月16日
平成最後の高校サッカー男女決勝
女子決勝 星槎国際湘南 1 (前半 1-0) 0 常盤木学園
星槎国際湘南、優勝おめでとうございます。創部からの年数よりも、やっぱり内容の濃さが大切なのだと今更ながら気づかされた大会でした。
試合を決めたのはたった一本のFKでしたが、その一本が唯一無二のスーパーキックでした。
もう一度やってみろなんて言われても不可能でしょうし、ましてやセーブなんて無理な質のブレ球系の高速シュートでしたね。
ただ、試合内容としてはそんなにレベルの高いものではなく、中盤から相手裏のスペース狙いのボールを入れてくるのみの常盤木、DFラインから横パス多用で丁寧にボールを繋ぐ星槎、という図式であり、沖野るせりの鋭いクロスや加藤ももの破壊力抜群のシュートという「ハッ」とするプレイもあったものの、お互いがチームとしての鋭さに欠けていたように感じましたね。
試合を分けたポイントとして、一つ目は運も含めたGKのセーブ力の差(たった数センチ程度の差ですが)ですね。
もうひとつは10番を背負うプレイヤーの出来でしょうか。 星槎の10番の展開力・守備力のほうが常盤木の10番の判断力・決定力を上回っていたと思います。
また、常盤木のほうに多く見られましたが、掬い上げみたいな感じで強引にボールを運ぼうとして相手に引っ掛けられ、ボールを奪われて流れを断ち切ってしまうプレーが散見されましたが、あれはあまり意味のないプレーと思いました。
あのようなプレーよりはむしろ後方にボールを戻してしっかり作り直すという戦略がベターでは?と考えますね。
昨年は順心には千葉、作陽には蓮輪というゲームをコントロールできるプレイヤーが居ましたが、今回では不在でした。
来年は今回2年生主体だった順心を中心に伝統校らが巻き返しを図ってくると思いますが、そろそろ高校女子にもチームカラーの多様性が出てきたと感じた大会でしたし、群雄割拠の様相を呈してきて非常に楽しみです。
男子決勝 青森山田 3 (前半 1-1) 1 流通経済柏
試合の入りはお互い慎重で硬かったですが徐々にほぐれてきてからは激しい試合になりました。
一言で言えば【プロフェッショナル高校サッカー集団】の流経柏、【現在のサッカー潮流のトレンド】の山田、となるのではないでしょうか。
特に青森山田のデュエル・ショートカウンター・フィジカルインテンシティはハイレベルでした。
青森山田のサッカーを見ていると、局面の個人の勝敗が積み重ねられていって得点を生み出し、勝利をもたらした印象が強いです。数年前のポゼッションサッカーから高校サッカーの主流に変化が起こっていると思いましたね。
キーポイントはバスケス・バイロン!彼のおかげで優位に立った場面が多々ありましたし、逆転ゴールに繋がった強引な突破、守備への貢献等じわじわと流経柏を消耗させていったと見ていました。
檀崎もさすがの2得点とキレのあるプレーでしたし、関川の存在感も飛び抜けてはいましたが、自分としてはMVPはバスケス・バイロンだと思いました。
勝負の結果を見ると、やっぱり守備だけでは勝てないし、セットプレイ頼みだけでは厳しいという事でしょうか。
それでも流経柏をみていると、全部員一丸となって競技に取り組めば毎年ハイレベルなチームになれるという、全国のフットボーラーの希望を見出した気になりましたね。
我が県には我が県の方法論があって然るべきでしょうし、そっくり真似するべきとは思いませんが、色々とヒントになるのではないでしょうか?
(情報班によるゲーム中の分析とか、GPS活用など)
来年もまた、県代表の健闘と面白い試合を期待してやまない決勝戦後でした。
星槎国際湘南、優勝おめでとうございます。創部からの年数よりも、やっぱり内容の濃さが大切なのだと今更ながら気づかされた大会でした。
試合を決めたのはたった一本のFKでしたが、その一本が唯一無二のスーパーキックでした。
もう一度やってみろなんて言われても不可能でしょうし、ましてやセーブなんて無理な質のブレ球系の高速シュートでしたね。
ただ、試合内容としてはそんなにレベルの高いものではなく、中盤から相手裏のスペース狙いのボールを入れてくるのみの常盤木、DFラインから横パス多用で丁寧にボールを繋ぐ星槎、という図式であり、沖野るせりの鋭いクロスや加藤ももの破壊力抜群のシュートという「ハッ」とするプレイもあったものの、お互いがチームとしての鋭さに欠けていたように感じましたね。
試合を分けたポイントとして、一つ目は運も含めたGKのセーブ力の差(たった数センチ程度の差ですが)ですね。
もうひとつは10番を背負うプレイヤーの出来でしょうか。 星槎の10番の展開力・守備力のほうが常盤木の10番の判断力・決定力を上回っていたと思います。
また、常盤木のほうに多く見られましたが、掬い上げみたいな感じで強引にボールを運ぼうとして相手に引っ掛けられ、ボールを奪われて流れを断ち切ってしまうプレーが散見されましたが、あれはあまり意味のないプレーと思いました。
あのようなプレーよりはむしろ後方にボールを戻してしっかり作り直すという戦略がベターでは?と考えますね。
昨年は順心には千葉、作陽には蓮輪というゲームをコントロールできるプレイヤーが居ましたが、今回では不在でした。
来年は今回2年生主体だった順心を中心に伝統校らが巻き返しを図ってくると思いますが、そろそろ高校女子にもチームカラーの多様性が出てきたと感じた大会でしたし、群雄割拠の様相を呈してきて非常に楽しみです。
男子決勝 青森山田 3 (前半 1-1) 1 流通経済柏
試合の入りはお互い慎重で硬かったですが徐々にほぐれてきてからは激しい試合になりました。
一言で言えば【プロフェッショナル高校サッカー集団】の流経柏、【現在のサッカー潮流のトレンド】の山田、となるのではないでしょうか。
特に青森山田のデュエル・ショートカウンター・フィジカルインテンシティはハイレベルでした。
青森山田のサッカーを見ていると、局面の個人の勝敗が積み重ねられていって得点を生み出し、勝利をもたらした印象が強いです。数年前のポゼッションサッカーから高校サッカーの主流に変化が起こっていると思いましたね。
キーポイントはバスケス・バイロン!彼のおかげで優位に立った場面が多々ありましたし、逆転ゴールに繋がった強引な突破、守備への貢献等じわじわと流経柏を消耗させていったと見ていました。
檀崎もさすがの2得点とキレのあるプレーでしたし、関川の存在感も飛び抜けてはいましたが、自分としてはMVPはバスケス・バイロンだと思いました。
勝負の結果を見ると、やっぱり守備だけでは勝てないし、セットプレイ頼みだけでは厳しいという事でしょうか。
それでも流経柏をみていると、全部員一丸となって競技に取り組めば毎年ハイレベルなチームになれるという、全国のフットボーラーの希望を見出した気になりましたね。
我が県には我が県の方法論があって然るべきでしょうし、そっくり真似するべきとは思いませんが、色々とヒントになるのではないでしょうか?
(情報班によるゲーム中の分析とか、GPS活用など)
来年もまた、県代表の健闘と面白い試合を期待してやまない決勝戦後でした。