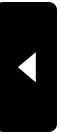2021年12月21日
論語(7)
「君子は矜なるも争わず。群すれど党せず」
君子は誇り高いが他者と争うことはしない。共同生活はするが徒党を組むことはしない。
*自立した人間は、確固たる自分を確立している。
「君子は和して同ぜず。小人は同じて和せず」
君子は和合はするが雷同しない。小人は雷同しても和合は出来ない。
*確固たる自己を作り上げていない人間と、自分を確立している者はこんなにも差がある。
「君子は泰にして驕らず。小人は驕りて泰ならず」
君子は(常に)堂々としていて、驕り高ぶったりしない。小人は驕り高ぶりやすいが、どこかセコセコしている。
*人格者は良い意味で自信に漲っているから、卑屈になったり、尊大になったりする必要がないのである。
「文質彬彬として、然る後に君子たり」
内容と形式が程よく両方備わって、はじめて君子(教養人、人格者)たり得るものだ。
「力 足らざる者は中道にして廃す。今 汝は限れり」
力不足の者は(それを言い訳に)中途でやめてしまう。今、あなたは「出来ない」と決めてかかってしまっている。
*自分で自分の限界をつくるな!ということ
君子は誇り高いが他者と争うことはしない。共同生活はするが徒党を組むことはしない。
*自立した人間は、確固たる自分を確立している。
「君子は和して同ぜず。小人は同じて和せず」
君子は和合はするが雷同しない。小人は雷同しても和合は出来ない。
*確固たる自己を作り上げていない人間と、自分を確立している者はこんなにも差がある。
「君子は泰にして驕らず。小人は驕りて泰ならず」
君子は(常に)堂々としていて、驕り高ぶったりしない。小人は驕り高ぶりやすいが、どこかセコセコしている。
*人格者は良い意味で自信に漲っているから、卑屈になったり、尊大になったりする必要がないのである。
「文質彬彬として、然る後に君子たり」
内容と形式が程よく両方備わって、はじめて君子(教養人、人格者)たり得るものだ。
「力 足らざる者は中道にして廃す。今 汝は限れり」
力不足の者は(それを言い訳に)中途でやめてしまう。今、あなたは「出来ない」と決めてかかってしまっている。
*自分で自分の限界をつくるな!ということ
Posted by godman at
14:02
│論語(ビギナーズクラシックス)
2021年12月20日
論語(6)
「古の学ぶ者は己の為にし、今の学ぶ者は人の為にす」
昔の学徒は自己鍛錬の為に学んでいたが、今の学徒は他人からの名声を得る(売名行為の)為に学んでいる。
*いつの時代も、真に学問を修める者と欲望達成の道具として学問を使う者に分かれる。「芸は身を助く」なら良いが、売名目的で学問を浪費するのは如何なものかと思う。
「之を知るは之を知ると為し、知らざるは知らずと為す、是 知るなり」
知っていることは知っていると言い、知らないことは正直知らないと答える。それが真に知るということなのだ。
*知らないことを知らないという事は、本当は難しいことである。
「之を如何せん、之を如何せん といわざる者には 吾(われ) 之を如何ともする無きのみ」
自ら「どのようにすればよいですか?」と質問すらしてこない者に対しては、私としてもどのようにも指導する事は出来ないものだ。
*主体性の無い者を指導することは出来ないという事だ。
「子貢 君子を問う」「まず行う。その言やしかる後、之に従う」
子貢が君子とはどのような人物か尋ねた。君子というものはまず実行し、その説明はその後に行うような人物であるとのことだった。
*実行が無ければ机上の空論となるのみだが、成功事例になったとして説明が完全に後付けというかこじつけになった場合、誤解を与えかねない。その点は注意しなくてはならない。
「君子はこれを己に求め、小人はこれを人に求む」
君子(教養人や人格者)は責任を自分に求めるが、小人(思慮分別の無い者)は責任を他人になすり付ける。
*思慮分別の無い者ほど、何事においても他力本願で、自ら状況を好転させる努力はしたがらないものなのである。
昔の学徒は自己鍛錬の為に学んでいたが、今の学徒は他人からの名声を得る(売名行為の)為に学んでいる。
*いつの時代も、真に学問を修める者と欲望達成の道具として学問を使う者に分かれる。「芸は身を助く」なら良いが、売名目的で学問を浪費するのは如何なものかと思う。
「之を知るは之を知ると為し、知らざるは知らずと為す、是 知るなり」
知っていることは知っていると言い、知らないことは正直知らないと答える。それが真に知るということなのだ。
*知らないことを知らないという事は、本当は難しいことである。
「之を如何せん、之を如何せん といわざる者には 吾(われ) 之を如何ともする無きのみ」
自ら「どのようにすればよいですか?」と質問すらしてこない者に対しては、私としてもどのようにも指導する事は出来ないものだ。
*主体性の無い者を指導することは出来ないという事だ。
「子貢 君子を問う」「まず行う。その言やしかる後、之に従う」
子貢が君子とはどのような人物か尋ねた。君子というものはまず実行し、その説明はその後に行うような人物であるとのことだった。
*実行が無ければ机上の空論となるのみだが、成功事例になったとして説明が完全に後付けというかこじつけになった場合、誤解を与えかねない。その点は注意しなくてはならない。
「君子はこれを己に求め、小人はこれを人に求む」
君子(教養人や人格者)は責任を自分に求めるが、小人(思慮分別の無い者)は責任を他人になすり付ける。
*思慮分別の無い者ほど、何事においても他力本願で、自ら状況を好転させる努力はしたがらないものなのである。
Posted by godman at
13:46
│論語(ビギナーズクラシックス)
2021年12月17日
論語(5)
「君子は文を以て友と会し、友を持って仁を輔(たす)く」
君子(教養人)は学芸を通じて友と交わり、その友情はお互いの人格を高めることに益する。
*専門分野や修めた趣味を通じた友人を指すのではないかと思う。
「子貢、仁を為すを問う」「この邦(くに)に居るや其の大夫の賢なる者につかえ、その士の仁なる者を友とせよ」
子貢が(人の)道の実践方法を問うた。(対して)自国においては重臣の中の賢臣を選んで仕えること、同僚の中の人格者を選んで親しくすることがその方法である。
*良い手本と良好な交友環境が、自己啓発や道理の実践のためには手っ取り早い。付き合う人物はしっかりと見極め選ばねばならない。
「直なるを友とし、諒なるを友とし、多聞なるを友とするは益するなり。便癖(べんへき)なるを友とし、善柔なるを友とし、便佞(べんねい)なるを友とするは損なうなり」
正直、義理堅い、博識、このような友は有益である。媚びる、表裏がある、口が巧い、このような友は有害である。
*自分に有害な者と交わってはならない。人物観察は重要なテーマである。
「日々に其の亡き所を知り、日々に其の能くする所を忘るる無くんば、学を好むというべきのみ」
日々新しいことを知り復習を怠らない。これが学問を好むということである。
*新たな発見の喜びと、日々反復する考察が学問の面白さ、奥深さなのであろう。
「事に敏に、言に慎み、有道に就きて正す。学を好むというべきなり」
なすべき仕事は素早くこなし、言葉数は少なくて出しゃばらず、意見があれば先ず優れた人格者を訪ねて正してもらう。これが好学の士というものだ。
*仕事が出来て、感情を露わにせず、独断に走らない人物が「好学の士」像である。
君子(教養人)は学芸を通じて友と交わり、その友情はお互いの人格を高めることに益する。
*専門分野や修めた趣味を通じた友人を指すのではないかと思う。
「子貢、仁を為すを問う」「この邦(くに)に居るや其の大夫の賢なる者につかえ、その士の仁なる者を友とせよ」
子貢が(人の)道の実践方法を問うた。(対して)自国においては重臣の中の賢臣を選んで仕えること、同僚の中の人格者を選んで親しくすることがその方法である。
*良い手本と良好な交友環境が、自己啓発や道理の実践のためには手っ取り早い。付き合う人物はしっかりと見極め選ばねばならない。
「直なるを友とし、諒なるを友とし、多聞なるを友とするは益するなり。便癖(べんへき)なるを友とし、善柔なるを友とし、便佞(べんねい)なるを友とするは損なうなり」
正直、義理堅い、博識、このような友は有益である。媚びる、表裏がある、口が巧い、このような友は有害である。
*自分に有害な者と交わってはならない。人物観察は重要なテーマである。
「日々に其の亡き所を知り、日々に其の能くする所を忘るる無くんば、学を好むというべきのみ」
日々新しいことを知り復習を怠らない。これが学問を好むということである。
*新たな発見の喜びと、日々反復する考察が学問の面白さ、奥深さなのであろう。
「事に敏に、言に慎み、有道に就きて正す。学を好むというべきなり」
なすべき仕事は素早くこなし、言葉数は少なくて出しゃばらず、意見があれば先ず優れた人格者を訪ねて正してもらう。これが好学の士というものだ。
*仕事が出来て、感情を露わにせず、独断に走らない人物が「好学の士」像である。
Posted by godman at
13:32
│論語(ビギナーズクラシックス)
2021年12月16日
論語(4)
「賢を賢として色をかろんじ、父母に仕えて能く其の力をつくし、朋友と交わり言いて信有り」
夫婦は互いに相手の長所・美徳を見いだし合うことが大切で容姿などは二の次である。父母に対しては出来る限りの孝行をつくせ。友人との交際は言行が一致するよう信義を守れ。
「知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼(おそ)れず」
賢人は迷わない、人格者は心静かである、勇者は恐れない。
「義を見て為さざるは、勇無きなり」
正義だと分かっていながら実行しないのは勇気がないからだ。
*正義=やるべき事、と考えても良いだろう。
「死生は命有り、富貴は天にあり」
人の生き死には運命によるものである。地位・財産は天の定めによる。
*生き死には確かに運命によると思うが、地位や財産は才能と努力による部分も無視できないのではないだろうか。
「老者 之を安んじ、朋友 之を信じ、少者 之を懐けん」
老人には心が安んぜられるよう接し、友人にはまごころを尽くす。後輩へは慈しみの心で対することである。
*現役を退いた老人へは尊敬の念を持ち、大目に見ることが肝要である。友人とは信頼と誠意をもって交流する。後輩に対しては長い目で見てあげることが大人の人付き合いである。
夫婦は互いに相手の長所・美徳を見いだし合うことが大切で容姿などは二の次である。父母に対しては出来る限りの孝行をつくせ。友人との交際は言行が一致するよう信義を守れ。
「知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼(おそ)れず」
賢人は迷わない、人格者は心静かである、勇者は恐れない。
「義を見て為さざるは、勇無きなり」
正義だと分かっていながら実行しないのは勇気がないからだ。
*正義=やるべき事、と考えても良いだろう。
「死生は命有り、富貴は天にあり」
人の生き死には運命によるものである。地位・財産は天の定めによる。
*生き死には確かに運命によると思うが、地位や財産は才能と努力による部分も無視できないのではないだろうか。
「老者 之を安んじ、朋友 之を信じ、少者 之を懐けん」
老人には心が安んぜられるよう接し、友人にはまごころを尽くす。後輩へは慈しみの心で対することである。
*現役を退いた老人へは尊敬の念を持ち、大目に見ることが肝要である。友人とは信頼と誠意をもって交流する。後輩に対しては長い目で見てあげることが大人の人付き合いである。
Posted by godman at
15:03
│論語(ビギナーズクラシックス)
2021年12月15日
論語(3)
「君子の徳は風なり。小人の徳は草なり。草 之に風を加うれば必ず伏す。」
為政者の品位は風、民衆の品位は草に例えうる。草に風が吹けば必ずなびき伏すものだ。
位の高い者が規範となる行動をとれば、一般民衆はそれに影響されるものである。
「君子儒となれ、小人儒となるなかれ」
教養人であれ、知識人に終わるなかれ。
「後生畏るべし。いずくんぞ来者の今に如かざるを知らんや。四十、五十にして聞こゆる無きは、其れまた畏るるに足らざるのみ」
若い者を侮ってはならない。後輩よりも現役の者の方が、必ずしも優れているとは言い切れないからだ。ただし、四十・五十になっても名を成せない(成果が上がらない)ような者なら取るに足らないであろう。
「学びて思わざれば則ちくらし、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し」
知識や情報をたくさん得ても、思考しなければ生かし方が分からず宝の持ち腐れである。逆に思考するばかりで知識や情報を欠いているようだと独善的になってしまう。
為政者の品位は風、民衆の品位は草に例えうる。草に風が吹けば必ずなびき伏すものだ。
位の高い者が規範となる行動をとれば、一般民衆はそれに影響されるものである。
「君子儒となれ、小人儒となるなかれ」
教養人であれ、知識人に終わるなかれ。
「後生畏るべし。いずくんぞ来者の今に如かざるを知らんや。四十、五十にして聞こゆる無きは、其れまた畏るるに足らざるのみ」
若い者を侮ってはならない。後輩よりも現役の者の方が、必ずしも優れているとは言い切れないからだ。ただし、四十・五十になっても名を成せない(成果が上がらない)ような者なら取るに足らないであろう。
「学びて思わざれば則ちくらし、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し」
知識や情報をたくさん得ても、思考しなければ生かし方が分からず宝の持ち腐れである。逆に思考するばかりで知識や情報を欠いているようだと独善的になってしまう。
Posted by godman at
13:59
│論語(ビギナーズクラシックス)