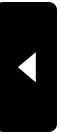2021年07月09日
呂氏春秋(31)

【Ⅳ 冬の節 ~陰陽争い、諸生蕩く~】
(死は人の免れざるところ)
「明確に生の意義を知ることは聖人の要務である。明確に死の意義を知ることは聖人の究極目的である。生の意義を知るものは”養生の道”に従い、死の意義を知るものは”安死の道”に在る。この2点(道)は聖人だけが到達できる境地である。」
(養生の道、安死の道、の二つは聖人でなければ到達できない究極の処であるという。生を養い、安らかに死すというのはなんとなくイメージできるが、その境地に明確に至るのはやはり至難の業なのだろう。)
2021年07月08日
呂氏春秋(30)

(政治は民心を得ること)
「民心を得ることは千里四方の土地を得ることより素晴らしい」
(周の文王が智者であったことは、民心を得ることの大切さを知っていたからであり、それを実践した事でもわかる。後に国として勢いを得た周は殷を倒すことが出来たのである。)
(なぜ的にあたるのか)
「聖人はうわべの存亡や賢不祥を問題にしないで、こうなった真の理由とは何か?を知ろうと努める。」
(本当に物事を理解できる人物というのは、うわべにとらわれずにその真理をつかもうとする、の意。うわべにとらわれるのは全て【欲】によると自分は思っていて、真理をつかむには無欲でなくてはならないと思っている。)
(誠実さの力)
「(自らが)物事に誠実であればそれは自ずと外に感じ表れ、自分に感動するものがあれば自然と人にも影響するものである。」
(誠実な人格は、知らず知らずのうちにその外見・容貌に表れるものである。また、誠実な人格の人が感動すると、その感情は他人にも伝播し影響する。逆に、狡猾な人格や悪意に溢れた人格も同様に表れ影響するであろう。)
2021年07月07日
呂氏春秋(29)

(相手の力を利用すること)
「用兵はその場の大勢に因循即応することを貴ぶ。因循即応とは敵の険阻に応じて自己の防衛線をつくり、敵の謀略に応じて自己の計画を立てることである。用兵は(敵が)勝つことが出来ない態勢をつくることを貴ぶ。こちらが(敵が)勝つことが出来ない態勢を守り、勝てる敵と戦えば軍隊が負けることは無い。用兵の勝利というものは敵の失敗による。隠密な者はあからさまな行動の者に勝ち、目立たぬ動きはあらわな作戦に勝ち、力を蓄えた者はばらばらな兵力に勝ち、集中した勢いは分散した戦力に勝つ。」
(因循即応、絶対的守備力、相手の失策を見逃さない、この三点が勝利の方程式。これはどんな事柄にも当てはまると思う。この節には、本質を理解しているものは自分の能力を大切にし、他人の能力を羨ましがって欲しがったりしないとの記述もあり、まさしくその通りと共感した。)
(秦の繆公の徳)
「徳を施し人を愛すれば民衆は君主を親愛し、民衆が君主を親愛すれば誰もが君主のために喜んで生命を投げ出して尽くすものである。」
(ギブアンドテイク、古代中国にもその考えがあったということか。そして民衆に好かれるような人徳がないと国や行政区のトップとして不足だということであろう。我が国、我が県、我が市の首長は果たしてどのくらいその点を充たしているのだろう。)
2021年07月06日
呂氏春秋(28)

(用兵の急務)
「用兵は素早く行動して勝利を得るのが良い。素早く速やかな態勢作りは戦って勝利を収める原因である。しかし軍は同じ場所にじっと留まってはいけない。留まってはいけないことを知っていれば、危機に際して上手く逃れることが出来る。」
(相手より早く勝利の要因を押さえ、自軍の態勢を盤石にしたうえで、先手を取って行動することが用兵の要であり確実な勝利の方法である。ただし、常に臨機応変の意識を持ちあまり構えすぎないことが裏をかかれた時に的確に対処できる、の意か。何も戦闘に限らず、ビジネスや勝負事、危機管理など色々な事象に応用できる考え方である。)
(気力こそ勝敗のもと)
「民衆は常に勇敢でもなく、かといって常に臆病でもない。用兵をよくする者は(ごく自然に)あらゆる民を(自発的に)戦闘に動員し、武芸のない者でも住民全てを戦闘に参加させる。それは、その場の勢いがそうさせるのである。」
(非戦闘員である民衆であっても、勢いのある軍隊、戦上手の将帥の元には自然に集まり、よく戦う、ということ。恐らくは勢いのある軍隊・戦上手の将帥の指揮下では危険度が少なく、一緒に戦っていれば安全・安心という集団心理が働くのではないか?故に戦闘への恐怖心が薄れ、我も我もという心理になるのではないだろうか。)
2021年07月05日
呂氏春秋(27)

(義兵は人を生かす)
「正義の軍の赴くところが遠くなればなるほど、(道中の)多くの民衆が懐き、戦うことなくして民衆は教化に従い服するものである。」
(正義の軍は民衆に歓迎されるから、その行程が遠くへ向かえば向かうほど、支持する民衆が増えてゆく。そうなれば最小限の犠牲で領土拡張が出来るし、平和に国を治められる、と述べているのだろう。しかしながら、正義の軍とはどのような軍なのか?定義が自己の都合によって変わるようならば、これは詭弁であろう。)
(兵は天下の凶器)
「およそ兵は天下の凶器であり、勇気の凶徳である。行使するのはやむを得ない事情からのことである。」
(軍兵は人を殺傷する凶器であり、決して肯定できるものではないが、それを行使することで結果的に最小限の犠牲で、害悪を取り除ける場合にのみ行使すべきである、と主張している。これも軍隊や兵器の保有を肯定する戦国期特有の論理であろう。今の世の中でこれをやると、兵器が発達しすぎていて恐らく収拾できない事態に陥る。)