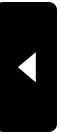2022年02月03日
荀子(22)
《天論》
「人間界に吉凶が有るのは何故か。(それは)人間が合理的に行動すれば吉、でたらめに行動すれば凶、となるに過ぎないからだ」
*吉凶の源は全て自分自身にある。要は為るべくして為るということであり、それを自分以外のものに原因を求めるのは思い違いも甚だしい。
「天には天の役割が有り、人間には人間の役割が有る」
*荀子の云う、【分】を守れという事だろう。
「何事にも正しい行為を心掛け、健全な生活態度を持して自分の生命を損なわない事、これを 天を知る という」
*しっかりと考えて真っ当に生きることが天(命)をしることになる。
「心の乱れを取り去る、正しい行いに努める、思慮を深める、古代に学ぶ、これらは個人の能力で達成できうる 人事(人に出来る事) である」
*内面を磨くことは個人でも十二分に出来るということである。
「(本来備えている)人間の力を忘れて、天を慕ってばかりいると、結局、万物の実態を見失ってしまう」
*他力本願への戒め。自分出来る事は自分で努力しないといけない。
「人間界に吉凶が有るのは何故か。(それは)人間が合理的に行動すれば吉、でたらめに行動すれば凶、となるに過ぎないからだ」
*吉凶の源は全て自分自身にある。要は為るべくして為るということであり、それを自分以外のものに原因を求めるのは思い違いも甚だしい。
「天には天の役割が有り、人間には人間の役割が有る」
*荀子の云う、【分】を守れという事だろう。
「何事にも正しい行為を心掛け、健全な生活態度を持して自分の生命を損なわない事、これを 天を知る という」
*しっかりと考えて真っ当に生きることが天(命)をしることになる。
「心の乱れを取り去る、正しい行いに努める、思慮を深める、古代に学ぶ、これらは個人の能力で達成できうる 人事(人に出来る事) である」
*内面を磨くことは個人でも十二分に出来るということである。
「(本来備えている)人間の力を忘れて、天を慕ってばかりいると、結局、万物の実態を見失ってしまう」
*他力本願への戒め。自分出来る事は自分で努力しないといけない。
2022年02月02日
荀子(21)
《議兵③》
「他国を併合する方法は三つある。徳による併合、力による併合、富による併合、である」
徳による併合→敬われ、慕われ、帰属することを望まれ、人民に信頼される。
力による併合→民心は離反し、軍費はかさみ、権威を失い、軍事力は弱る。
富による併合→金と食料を目当てにされ、国庫が空になる。
「徳によって併合すれば王者になる。力によって併合すれば弱くなる。富によって併合すれば貧しくなる」
*被併合国の人民に受け入れられるような併合の仕方以外は、自国を傾ける元凶なのである。余程の事でなければ、他国を侵すべきではないし、かえって損害を招くもと。某アジアの大国は、この法則に反しているが、果たしてどうなるのか。
・(あらゆる)戦争は決して利益の為であってはならない。必ず人民の為でなくてはならない。勝利を得るのは人民の支持を得たものだけである。
「他国を併合する方法は三つある。徳による併合、力による併合、富による併合、である」
徳による併合→敬われ、慕われ、帰属することを望まれ、人民に信頼される。
力による併合→民心は離反し、軍費はかさみ、権威を失い、軍事力は弱る。
富による併合→金と食料を目当てにされ、国庫が空になる。
「徳によって併合すれば王者になる。力によって併合すれば弱くなる。富によって併合すれば貧しくなる」
*被併合国の人民に受け入れられるような併合の仕方以外は、自国を傾ける元凶なのである。余程の事でなければ、他国を侵すべきではないし、かえって損害を招くもと。某アジアの大国は、この法則に反しているが、果たしてどうなるのか。
・(あらゆる)戦争は決して利益の為であってはならない。必ず人民の為でなくてはならない。勝利を得るのは人民の支持を得たものだけである。
2022年02月01日
荀子(20)
《議兵②》
「将軍たるものは、六つの術 五つの均衡 三つの急所 を肝に銘じなければならない」
六術→①布告は厳しく、発令は威を以て②賞罰は的確に③布陣は周到堅固に④部隊移動は慎重迅速に⑤索敵・状況把握は深く⑥必勝の策のみ用いる
五均衡→①地位にしがみつかない②勝利よりも負けない事を重視③敵を疎かにするな(主観で決めつけない)④自軍の不利な点を見落とすな⑤計画は慎重に、軍費は惜しむな
三急所→①みすみす危険な場所へ布陣しない②勝ち目のない戦は仕掛けない③人民を欺いてはならない(大本営発表のようなもの)
「人間というものは褒賞を目当てに行動する限り、逆に損をすると分かればたちまち止めてしまう。だから賞罰で脅かしたりすかしたりするだけでは命懸けで働かせることは出来ない」
*命懸けで働いてもらうためには、結局は「信頼」と「魅力」が必要であり、それは天性のものではないかと思う。
「一方で爵位と褒賞を掲げ、一方で刑罰と恥辱を掲げて原則を明らかに示せば、誰もが知らず知らずのうちに善良になるに決まっている」
*社会規範が定まっていれば、悪いことをするのは損で良いことをすれば得だ、という損得勘定が働くので普通は善良になる。規範を歯牙にもかけない利己的な者は、いずれ刑罰の網に絡めとられ、恥辱にまみれることになるのである。
「将軍たるものは、六つの術 五つの均衡 三つの急所 を肝に銘じなければならない」
六術→①布告は厳しく、発令は威を以て②賞罰は的確に③布陣は周到堅固に④部隊移動は慎重迅速に⑤索敵・状況把握は深く⑥必勝の策のみ用いる
五均衡→①地位にしがみつかない②勝利よりも負けない事を重視③敵を疎かにするな(主観で決めつけない)④自軍の不利な点を見落とすな⑤計画は慎重に、軍費は惜しむな
三急所→①みすみす危険な場所へ布陣しない②勝ち目のない戦は仕掛けない③人民を欺いてはならない(大本営発表のようなもの)
「人間というものは褒賞を目当てに行動する限り、逆に損をすると分かればたちまち止めてしまう。だから賞罰で脅かしたりすかしたりするだけでは命懸けで働かせることは出来ない」
*命懸けで働いてもらうためには、結局は「信頼」と「魅力」が必要であり、それは天性のものではないかと思う。
「一方で爵位と褒賞を掲げ、一方で刑罰と恥辱を掲げて原則を明らかに示せば、誰もが知らず知らずのうちに善良になるに決まっている」
*社会規範が定まっていれば、悪いことをするのは損で良いことをすれば得だ、という損得勘定が働くので普通は善良になる。規範を歯牙にもかけない利己的な者は、いずれ刑罰の網に絡めとられ、恥辱にまみれることになるのである。
2022年01月31日
荀子(19)
《議兵①》
・策士は策に溺れる。策士たろうとするよりも基本的なものを充実させよ、というのが荀子の策略論である。
「軍が礼・義に基づき、この上なく結束していれば天下を制することが出来る」
*軍規が遵守され統制が取れている、まとまりが有り品行方正である、という組織は頂点に立てるのである。
「将軍たるものは、①判断を下す際、迷わないこと ②行動に際し原則を誤らないこと ③後悔するような作戦の展開をしないこと ④作戦は徹底的にやり通すこと が肝要である」
*将軍に限らず、組織のリーダーはこの4点は留意しておいて損はない。この原則に加えて臨機応変の柔軟性を兼ね備えれば盤石である。
・策士は策に溺れる。策士たろうとするよりも基本的なものを充実させよ、というのが荀子の策略論である。
「軍が礼・義に基づき、この上なく結束していれば天下を制することが出来る」
*軍規が遵守され統制が取れている、まとまりが有り品行方正である、という組織は頂点に立てるのである。
「将軍たるものは、①判断を下す際、迷わないこと ②行動に際し原則を誤らないこと ③後悔するような作戦の展開をしないこと ④作戦は徹底的にやり通すこと が肝要である」
*将軍に限らず、組織のリーダーはこの4点は留意しておいて損はない。この原則に加えて臨機応変の柔軟性を兼ね備えれば盤石である。
2022年01月28日
荀子(18)
《臣道》
「理想的な臣下を使えば理想的な君主になれる。役に立つ臣下を使えば強国の君主になれる」
*個人の力、能力などたかが知れている。チームとしての構成が組織の良し悪しを決めるのだと思う。
「ただ自分の俸禄と食客を増やすことしか考えない臣下は国賊である」
*この場合の「臣下」はそれなりのポストに就いている人物であろう。自分の利益と名声に終始している人物は給料泥棒のようなもので、逆に言えばそういう人物に重要ポストを与えるべきではない。
「諫臣、争臣、輔臣、弼臣、は国家の柱石であり君主の宝である」
①諫臣:聞き入れてもらえなければ国を去る決心で進言する臣下
②争臣:聞き入れてもらえなければ命を捨てる覚悟で進言する臣下
③輔臣:グループを率い、組織力で君主の意志を変える臣下
④弼臣:君主の主権を奪ってまで国の危難を救い君主の名誉を守る臣下
*イエスマンばかりでは駄目という事。また、トップの資質には、部下の苦言に耳を傾けることが出来るかどうかが問われるのだろう。
「名君は臣下の協力を求めるが、暗君は何でも一人でやりたがる」
*個人の力を過信し、組織力を軽視するトップは愚か者である。
「欠点を直してやるには相手の不安を、方針を変えさせるには相手の悩みを、心得を悟らせるには相手の喜びを、取り巻き・小人共を追い出すには相手の怒りを利用するとよい」
*説得術の一つであろう。特に佞臣であることが多い取り巻き連中・小人連中を追い出すには、「思慮分別の浅い」人間を怒らせて向こうから出ていくように仕向けるのが後腐れない上策と感じた。
「理想的な臣下を使えば理想的な君主になれる。役に立つ臣下を使えば強国の君主になれる」
*個人の力、能力などたかが知れている。チームとしての構成が組織の良し悪しを決めるのだと思う。
「ただ自分の俸禄と食客を増やすことしか考えない臣下は国賊である」
*この場合の「臣下」はそれなりのポストに就いている人物であろう。自分の利益と名声に終始している人物は給料泥棒のようなもので、逆に言えばそういう人物に重要ポストを与えるべきではない。
「諫臣、争臣、輔臣、弼臣、は国家の柱石であり君主の宝である」
①諫臣:聞き入れてもらえなければ国を去る決心で進言する臣下
②争臣:聞き入れてもらえなければ命を捨てる覚悟で進言する臣下
③輔臣:グループを率い、組織力で君主の意志を変える臣下
④弼臣:君主の主権を奪ってまで国の危難を救い君主の名誉を守る臣下
*イエスマンばかりでは駄目という事。また、トップの資質には、部下の苦言に耳を傾けることが出来るかどうかが問われるのだろう。
「名君は臣下の協力を求めるが、暗君は何でも一人でやりたがる」
*個人の力を過信し、組織力を軽視するトップは愚か者である。
「欠点を直してやるには相手の不安を、方針を変えさせるには相手の悩みを、心得を悟らせるには相手の喜びを、取り巻き・小人共を追い出すには相手の怒りを利用するとよい」
*説得術の一つであろう。特に佞臣であることが多い取り巻き連中・小人連中を追い出すには、「思慮分別の浅い」人間を怒らせて向こうから出ていくように仕向けるのが後腐れない上策と感じた。