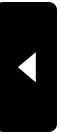2022年01月27日
荀子(17)
《富国④》
「政令は原則が貫かれ、基準が明らかでなくてはならない。基準が明確でなければ人々は疑い深くなり、社会の気風が刺々しくなって人民(世論)はまとまらない」
*そのまま全て今に通用する。政治だけでなく、組織の運営にも当てはまるし、社会生活を円滑にする意味でも非常に重要な事項である。
「ともに賢人で甲乙つけられない場合は、近親者を優先的に重用する。ともに有能で甲乙つけられない場合は、縁故者を優先的に採用する」
*自分は全く逆だと思う。韓非子なども、近親者や縁故者は油断ならない者と言っているし、現代では当人達が批判・非難・猜疑の視線にさらされ、かえって悪事に手を染める事態になると思う。
「名君は必ず財政の調整に心がけ、国庫の充足よりも地方の開発に力を入れ、無理な徴収は行わない。これこそ最高(最善)の政策というものである」
*財政運営、地方のインフラ整備、負担の軽減、といずれも現在の我が国や自治体が為すべき課題である。
「一般に他国を攻撃するのは、名声の為か、利益の為か、怒りの為か、のいずれかである」
*要は欲望と憎悪が戦争を引き起こすのだろう。複雑な事情があったとしても、開戦に踏み切らせるのはトップの気持ち次第なのである。
・仁君の国家は、あらゆる国家の不利益を回避できると荀子は述べている。
・「分」を超えた行いは世を乱すもとであり、誰もが「分」の枠内で生きなければならない。その為に【治める者】と【治められる者】をはっきりと分離しなければならない、というのが荀子の説でもある。
「政令は原則が貫かれ、基準が明らかでなくてはならない。基準が明確でなければ人々は疑い深くなり、社会の気風が刺々しくなって人民(世論)はまとまらない」
*そのまま全て今に通用する。政治だけでなく、組織の運営にも当てはまるし、社会生活を円滑にする意味でも非常に重要な事項である。
「ともに賢人で甲乙つけられない場合は、近親者を優先的に重用する。ともに有能で甲乙つけられない場合は、縁故者を優先的に採用する」
*自分は全く逆だと思う。韓非子なども、近親者や縁故者は油断ならない者と言っているし、現代では当人達が批判・非難・猜疑の視線にさらされ、かえって悪事に手を染める事態になると思う。
「名君は必ず財政の調整に心がけ、国庫の充足よりも地方の開発に力を入れ、無理な徴収は行わない。これこそ最高(最善)の政策というものである」
*財政運営、地方のインフラ整備、負担の軽減、といずれも現在の我が国や自治体が為すべき課題である。
「一般に他国を攻撃するのは、名声の為か、利益の為か、怒りの為か、のいずれかである」
*要は欲望と憎悪が戦争を引き起こすのだろう。複雑な事情があったとしても、開戦に踏み切らせるのはトップの気持ち次第なのである。
・仁君の国家は、あらゆる国家の不利益を回避できると荀子は述べている。
・「分」を超えた行いは世を乱すもとであり、誰もが「分」の枠内で生きなければならない。その為に【治める者】と【治められる者】をはっきりと分離しなければならない、というのが荀子の説でもある。
2022年01月26日
荀子(16)
《富国③》
「賞罰を権威をもって行えば能力に応じた職務配置が出来るようになる。そうなれば万事が無理なく治まり、いかなる不測の事態にも対処できる」
*法令の順守と、人材の適正配置を実践できれば、組織運営は盤石になる。トップはそういう機構を創り上げることが大切である。
「民生の向上を口実にして国家の大事をなおざりにするような政治は、永続きせず、何をやっても実を結ばず、功績も上がらない、という邪道なものである」
*昨今のバラマキ行政を見ているとナルホドと頷ける。国家の大事、とは何か。それは国民の生命財産の保障と、産業と文化の保護育成だと思う。
・人気取りも強圧も、どちらも君主に自信がなく、民衆の自発性を信じることが出来ていないことを表すものと断じている。
「賞罰を権威をもって行えば能力に応じた職務配置が出来るようになる。そうなれば万事が無理なく治まり、いかなる不測の事態にも対処できる」
*法令の順守と、人材の適正配置を実践できれば、組織運営は盤石になる。トップはそういう機構を創り上げることが大切である。
「民生の向上を口実にして国家の大事をなおざりにするような政治は、永続きせず、何をやっても実を結ばず、功績も上がらない、という邪道なものである」
*昨今のバラマキ行政を見ているとナルホドと頷ける。国家の大事、とは何か。それは国民の生命財産の保障と、産業と文化の保護育成だと思う。
・人気取りも強圧も、どちらも君主に自信がなく、民衆の自発性を信じることが出来ていないことを表すものと断じている。
2022年01月25日
荀子(15)
《富国②》
「人はこの世に生きる以上、社会を形成しないわけにはゆかない。社会に【分】がなければ争いが起こる。争いが起これば秩序は乱れる。そうなれば民衆は路頭に迷う」
*荀子は【分】を遵守することをしばしば力説する。人間は、与えられたキャラクターをしっかり演じ切ることが幸せなのかもしれない。
「【分】が無いことほど恐ろしいことは無いし、【分】が有ることほど有り難いことはない。君主はこの【分】を管轄する要である」
*基準や分担がないと社会は上手く回らないのは周知の事実である。
「君主たるもの、国を治めるだけの英知と、民生を安定させるだけの慈愛と、人民を教化するだけの徳がなくてはならない」
*簡単なようでいて極めて難しいことだが、国家のリーダーの理想像であろう。しかし、現代の「システム化」された統治方式ではこのような人物が出てくることは無い。
「天下を等しく充足させる要点は職分を明確化するにある」
*失業者対策の要点はこの方針にあるのかもしれない。
・君主は大局的な視野に立ち、目先の心配より民衆の活力を伸び伸びと発揮させるべきだ、と荀子は強調する。
「人はこの世に生きる以上、社会を形成しないわけにはゆかない。社会に【分】がなければ争いが起こる。争いが起これば秩序は乱れる。そうなれば民衆は路頭に迷う」
*荀子は【分】を遵守することをしばしば力説する。人間は、与えられたキャラクターをしっかり演じ切ることが幸せなのかもしれない。
「【分】が無いことほど恐ろしいことは無いし、【分】が有ることほど有り難いことはない。君主はこの【分】を管轄する要である」
*基準や分担がないと社会は上手く回らないのは周知の事実である。
「君主たるもの、国を治めるだけの英知と、民生を安定させるだけの慈愛と、人民を教化するだけの徳がなくてはならない」
*簡単なようでいて極めて難しいことだが、国家のリーダーの理想像であろう。しかし、現代の「システム化」された統治方式ではこのような人物が出てくることは無い。
「天下を等しく充足させる要点は職分を明確化するにある」
*失業者対策の要点はこの方針にあるのかもしれない。
・君主は大局的な視野に立ち、目先の心配より民衆の活力を伸び伸びと発揮させるべきだ、と荀子は強調する。
2022年01月24日
荀子(14)
《富国①》
「何を正しいと信じるかで知者と愚者が分かれる」
*これは恐らく、信念の有無と情報分析能力の有無を言っていると思う。もしくは信用対象が根拠が有るのか否か?というあたりだろう。
「全て弊害は欲望を放任することから起こる」
*己の欲望のほしいままに行動することは、絶対的に悪であり弊害だらけだというのは自分の持論でもある。
「節約すれば物質は余るし、ゆとりを与えれば人民は富む」
*当時は食糧確保が生活の重要な部分を占めていただろう。そのため、「備蓄」が重要な課題であったと思う。まずは倉庫の備蓄を充分にして、その余禄で人民に余裕を与えると、人民の生活が安定し生命財産を国家が保障できたのだと推察する。
「法に従って課税し、礼に従って倹約すれば物資はあり余る」
*適正な課税と、無駄のない循環型消費を心掛けることを説いている。
「金の力で人民にゆとりを与える方策は、以下のようなものである。租税を軽減し関所や市場の課税を公平にすること、高利貸しを減らして農民(生産従事人口)を増やすこと、労役を最小限度にとどめ農繁期を避けること、である」
*減税、公平な負担、生産従事人口の増大、産業の育成、と現代でも重要な方策が並んでいる。
「何を正しいと信じるかで知者と愚者が分かれる」
*これは恐らく、信念の有無と情報分析能力の有無を言っていると思う。もしくは信用対象が根拠が有るのか否か?というあたりだろう。
「全て弊害は欲望を放任することから起こる」
*己の欲望のほしいままに行動することは、絶対的に悪であり弊害だらけだというのは自分の持論でもある。
「節約すれば物質は余るし、ゆとりを与えれば人民は富む」
*当時は食糧確保が生活の重要な部分を占めていただろう。そのため、「備蓄」が重要な課題であったと思う。まずは倉庫の備蓄を充分にして、その余禄で人民に余裕を与えると、人民の生活が安定し生命財産を国家が保障できたのだと推察する。
「法に従って課税し、礼に従って倹約すれば物資はあり余る」
*適正な課税と、無駄のない循環型消費を心掛けることを説いている。
「金の力で人民にゆとりを与える方策は、以下のようなものである。租税を軽減し関所や市場の課税を公平にすること、高利貸しを減らして農民(生産従事人口)を増やすこと、労役を最小限度にとどめ農繁期を避けること、である」
*減税、公平な負担、生産従事人口の増大、産業の育成、と現代でも重要な方策が並んでいる。
2022年01月21日
荀子(13)
《王制⑦》
「君主の声価や国家の盛衰・存亡は外圧が無い時、何を本心から楽しみ、あるいは心配するかによって決まる」
*平常時こそ政治を引き締め、普段から不測の事態に備えておくことの大切さを説く。君主は常に自国民の生命財産の保証と生活の安定に腐心するのが責務である。
「国家が隆盛ならば、対外的にはいずれの勢力にも組(くみ)することなく中立政策を貫くべきである」
*戦国期ならではの現実論であろう。中国の戦国期は常に接している隣国との緊張状態が保たれていた。すなわち力関係を見極めて国家の存続を目指さねばならなかった。故に、○○国へ付く、というあからさまな外交態度はタブーであったろう。
・荀子が理想とする政治の指導理念は【王道】である。
・集団生活を営むのは人間の本能であるが、スムーズに運営するために強力な君権と「分」の必要性を説いている。また、その根拠が性悪論である。
・秩序を維持するため、各人がその身分に許された枠内で行動しなくてはならないが、これが「分」である。
・荀子の述べている『礼』は『法』と置き換えても同意である。
「君主の声価や国家の盛衰・存亡は外圧が無い時、何を本心から楽しみ、あるいは心配するかによって決まる」
*平常時こそ政治を引き締め、普段から不測の事態に備えておくことの大切さを説く。君主は常に自国民の生命財産の保証と生活の安定に腐心するのが責務である。
「国家が隆盛ならば、対外的にはいずれの勢力にも組(くみ)することなく中立政策を貫くべきである」
*戦国期ならではの現実論であろう。中国の戦国期は常に接している隣国との緊張状態が保たれていた。すなわち力関係を見極めて国家の存続を目指さねばならなかった。故に、○○国へ付く、というあからさまな外交態度はタブーであったろう。
・荀子が理想とする政治の指導理念は【王道】である。
・集団生活を営むのは人間の本能であるが、スムーズに運営するために強力な君権と「分」の必要性を説いている。また、その根拠が性悪論である。
・秩序を維持するため、各人がその身分に許された枠内で行動しなくてはならないが、これが「分」である。
・荀子の述べている『礼』は『法』と置き換えても同意である。