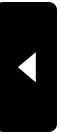2023年01月06日
氷川清話⑥

「貧貴強弱によって国々を別々に見るということはしない」
先進国だの途上国だの、大国だの小国だのを自分で勝手にランク付けして他国を判断してはいけないということ。日本人はその差別的視点を他国の人民に対してあてはめようとするきらいがある。
「公平無私の眼をもって世界の大勢上から観察を下して、その映ってくるままにこれを断ずる」
経済力や軍事力によらず、客観的な観察眼によって諸外国を判断することが重要かつ正確性を有することを述べている。
「自分で傑物がるのは実にみていられないよ」
今も昔も、自分をより大きく、身の丈以上に見せたがる人間は多いものだが、見識のある人間から見ればすぐに見抜かれる。
「政治をするには学問や知識は二番目で、至誠奉公の精神が一番肝心だ」
政治とは人民のために行うものだから、そこに私心があっては政治家ではありえない。
「八方美人主義ではその主義の奏効にばかり気を取られて、国家のために大事業をやることはできない」
あれもこれも、という方針や方策が定まらない状態では、結局大きな仕事を遂行するまでに息切れしてしまい、中途半端で終わってしまうのだろう。
「政治は理屈ばかりでゆくものではない」
政治は、結局人が人に対して行うものである。だから人情の機微を理解していないと絶妙に運用できない。
「行政改革ということはよく気を付けないと弱い者いじめになる。改革ということは公平でなくてはいけない。改革者が一番に自分を改革するのだ」
改革が弱い者いじめになるというのは何となく想像できる。そして、公平であるべきということにも納得できる。改革は、先ず耐性のある所から手を付け、一律ではなくきめ細かくやるべきなのだ。
2023年01月05日
氷川清話⑤

「熟考の上で決行すれば、やれないことは天下にないさ」
冷静に考えてみればその通りなのだが、平時には緊張感の欠如から熟考がおざなりになるし、緊急時には速さを求められて熟考できない場面が多々ある。常日頃の熟考と想定が、実行には不可欠である。
「北条氏が栄えたのはつまり倹(恭倹、倹約)のためで、滅びたのは驕り(驕慢、驕奢)のためだよ」
恭倹な態度をとり、倹約質素な生活が繁栄の礎であり、驕慢な態度になり、驕奢な生活を送れば滅亡するのは自明の理である。
「学者の学問は容易だけど、俺らがやる無学の学問は実に難しい」
学者の学問は学ぶための学問で、範囲も限られている。無学の学問とは、天下万民を導く術であり誰かに教わったり、唯一の正解があるものではない。
「(外交の秘訣は)心を明鏡止水の如くすることだ。ならば、機に臨み変に応じて事に処する方策が浮かび出るものだ」
「外交の極意は正心誠意にある。誤魔化しなどをやりかけるとかえってこちらの弱点を見抜かれるものだよ」
下手な芝居を打つよりは、正直に誠実に外交を展開すべき、というのはこの時代には現実的な対応だったのだろう。開国直後の日本の外交力は列強に比べ大人と子供ほどの差があったと思われる。
「国民がいま少し根気強くならなければ、とても(国家あげての)大事業はできない」
これも黎明期の国家の切実な状況を指しているように思う。弱小国家の日本が、何かを成し遂げようとしたら、国民もある程度の我慢を要するのは当然であったか。
「人間は生き物だから 気 を養うのが第一。気 さえ飢えなければ食物などは何でも構わない」
結局、人間は気力さえ折れなかったら、どうにかこうにか状況を打開できるようにできているものである。それにはやはり前向きであることも必要不可欠である。
2023年01月04日
氷川清話④

「政治家の秘訣は何もない。ただただ『正心誠意』の四文字ばかりだ」
私心のない、正直な人物こそ政治家向きとする勝の見解である。令和の日本には、政治屋ばかりで政治家は希少なように思える。
「何事も全て知行合一でなければいけないよ」
知識だけ、経験だけではいけないということ。実体験に裏打ちされた知識であることが大切なのだ。
「(信長は)民生のことには深く意を用いて、租税を減らし、民力を養い、大いに武を天下に用うるの実力を蓄えた」
民間の活力増強こそが国家繁栄の基礎であり、それがなければ国力の充実は図れやしない。
「今も昔も人間万事 金 というものがその土台である」
経済的安定がなければ、充実した人生は歩めない。経済的に困窮しながら、正義を貫くもの好きは稀である。衣食足りて...ということを現実的に肯定している。
「財政が困難になると、議論ばかりやかましくなって何の仕事もできない。そこへ付け込んで種々の魔がさすものだ」
経営が苦しい企業が悪事に手を染めたり、そのような企業で背信行為が引き起こされるのも、このような要因があるのかもしれない。しかし今の日本は「金がないふり」をしている政府(と財務省)に操られて、民間の財力がトコトン吸い上げられているようにも思える。
「学問学問と言っていると、口ばかり達者になって年上の者をやり込めるようになるよ。国家もその通りで、人民が理屈ばかり言っておっては、おっつけ貧乏してしまうだろう」
口ばっかりで仕事しないなら、貧乏になるのも当然であろう。
「貧乏人に金をくれてやるのでも、下手をするとかえって弊害を増すばかりだ」
バラまきばかりでは解決にならないことがある。補助金や公共事業もハード面の投資ばかりでは一部の業界の、そのわずかの部分しか潤わず、真に国民の為になるとは思えない。本当に必要としている人々を助けることができるシステムにこそ投資してほしいものだ。
2023年01月03日
氷川清話③

「漢学というものは決して悪い学問ではない。やりようによっては随分役に立つ。こんにちのように一向振るわない、というのは漢学をやる人が悪いからだ」
学者の人品が卑しければ素晴らしい学問分野でも没落するものである。学問とは人類全体、地球全体にとって有益で公平なものでなくてはならない。
「人間も(ある程度は)生まれが大事だ。小国でも貴族は(さすがに)貴族(な)だけの潔白な心を持っている」
環境(育ちや出自)によっても人間の品格は左右されるものだ。我々平凡人なら尚更である。
「陸奥(宗光)は、人物の部下としてその幕僚となるに適した人物で、人の長としてこれを統率するには不適当であった」
坂本龍馬配下で輝きを放った陸奥宗光のことを端的に表している言葉である。人には誰しも適材適所というものがあるのである。
「日本人ももう少し公共心というものを養成しなければ(国家としての)実績をつくりあげることはできまいよ」
我欲、利己的な心持ちが前面に出ていたのが維新の頃であったのか?国家や日本社会の利益を考えた事業を志す風潮の無さ、人物の少なさを憂いた言葉であろう。
「苦痛を顔色にも出さず、じっと辛抱しておると世の中は不思議なものでいつか景気(自己への評価のことか?)も回復するものです」
困難な状況にあっても心折れずに耐え忍いでいれば、必ずや挽回できるという実体験に基づいた深い言葉である。ただ耐え忍ぶだけでなく、コツコツと努力も絶やさないことは言うまでもないだろう。
「時勢は人を造るものだ」
加えて、【時勢に選ばれし者】が大人物になるのであろう。
2023年01月02日
氷川清話②

「自分の相場が下落したとみたら、じっとかがんでおればしばらくするとまた上がってくるものだ。その上がり下がりの十年を辛抱できる人は大豪傑だ」
不遇の時期があっても、腐らずに辛抱していればやがて上昇の時がやってくるものである。この十年を淡々と過ごせるような器量と自身の信念を有している者が大豪傑といえる。
「こんにち、自分から騒ぎ出して幾分か俗物どもに知られているやつらは、三十年も経たないうちに忘れられてしまうだろうよ」
自らの売名行為によってし有名になった人間は、中身を伴わなければ、いずれ忘れ去られる。しかし、三十年も持つとは少々驚きであるが...。
「天下の安危に関する仕事をやった人でなくては、後世に知られるものではない。ちょっと芝居をやったくらいでは天下に名は上がらないさ」
これも浅はかな売名行為を戒めたものであろう。
「西郷(隆盛)はどうも人に分からない所があったよ。大きな人間ほどそんなものさ」
「(横井)小楠はとても尋常の物差しではわからない人物で、かつ、一向ものにこだわりせぬ人であった。それゆえ一戸の定見というものはなかったけれど、機に臨み変に応じて物事を処置するだけの余裕があった」
勝の西郷隆盛評、横井小楠評である。西郷は大器量人、横井は大実務人だと自分は思う。
「人を用いる(採用した人物が一人前になる)には急ぐものではないということと、一つの事業は(少なくとも)十年たたねばとりとめの付かぬものだということさ」
人材登用と事業の評価は早急にはできないということである。速成した結末は、地盤が固まっていないから必ず傾くもの。自己啓発にもこれは当てはまると思う。しっかりした日々の歩みこそ大切なのだ。