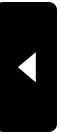2021年02月10日
左伝(13)

【中原休戦の時代】
斉の名宰相・晏嬰の若き日の言
「臣下たるものは、禄のためではなく国家の繁栄のためにつくすべきだ」
現代に当てはめるなら、「臣下」は政治家や役人というところであろう。こんにち、この心得が欠如している者のなんと多い事か。
なにも臣下(役人)だけの心得でもあるまい。自分なら「人間たるもの、金のためでなく精神の修養のためにつくすべきだ」って解釈する。
いわゆる理想論であるが、この言葉を基準に、正道を見失わないで生きてゆければいいのではないかと思う。
鄭の大政治家・子産の言葉①
「弾圧によって人の怨みを失くすことは出来ぬ。言論もこれと同じこと、弾圧するよりも聞くべきは聞いて、こちら(為政者)の薬とした方がよいのだ」
イエスマンの意見ばかりでなく、批判意見もキチンと聴いて自らの糧にしなさいなってこと。
最近の中国やミャンマーの情勢をみていると、とても危なっかしく感じるのは、この言葉が胸に残っているのと無関係ではないだろう。
鄭の大政治家・子産の言葉②
「天の働きは果てしなく深遠である。それに対し人間の働きの及ぶ範囲などごく狭いもの。人智によって天の意思を推測することがどうして出来ようか」
色々な解釈の仕方があると思うが、天の意思=天災、自然災害 と考えると現代にも当てはまると思う。また、原子力のような人間では完全に制御できないものも天の意思と考えれば、ストンと腑に落ちるのは自分だけだろうか。
鄭の大政治家・子産の言葉③
「政治には二つの方法がある。一つは緩やかな政治、もう一つは厳しい政治だ。緩やかな政治で人民を服従させることは余程の有徳者でないと難しく、失敗しやすい。だから、一般には厳しい政治姿勢をとった方がうまくいくのだ」
子産の政治方針である。緩やかな政治を水、厳しい政治を火に例え、水は一見怖くなく見えるため、かえって侮らせて水難を生じること、火は危険を感じさせるため、恐れて近寄らず結果として火傷の害も少ないと説明している。
このことを孔子は「人民というものは為政者が手綱を緩めればつけ上がりがちなものだ」と実に鋭く見抜いている。
いつの時代も、人間というものは玉石混合で様々な者が居るし、それこそ善良な市民から極悪非道の無法者まで同じ空間に存在している。そして、彼らが「大衆」になると周囲に同調して流され、善にも悪にもなりえる御し難い存在である、ということを揶揄していると感じている。